どうも、太陽です。(No44)
突然ですが、「2020年大学入試教育改革」は頓挫しました。
そして、従来の教育から転換して「「思考力・判断力・表現力」を見ることにシフトした!」と強調していました。
で、その手段として、国語の試験で「150字程度の決まった答えしか出なさそうな記述試験」に決まる寸前までいったのです。
僕は呆れました。
そんな150字程度の、しかも決まりきった答えしか、ほとんど許されない中での記述で「思考力なんて測れるわけがない!」と。
今回は、「では思考力とはどのようにしたら測れるのか?」という問いに答えていきたいと思います。
タイトルに答えはほぼ載っていますが、さらに詳細に考察していきますので、興味がある人は続きをお読み下さい。
思考力を訓練したい人へも、「思考力の測り方を知ることで応用できる」と思います。
1 従来の国語の試験。
まず、従来の国語の試験、特に共通テストの現代文について、問われている能力を解説していきます。
ズバリ、「読解力・知識・情報処理能力」(またはワーキングメモリ(短期記憶)も?)だけが問われており、それ以外は問われていません。
「長文の文章を書く力・新しい発想・アイデアを生み出す創造力・コミュ力など」は問われていません。
さらに、思考力も問われていません。
思考力の一部が測れるのは小論文ですが、約800文字〜1000文字程度なので、限界があります。
現代文の試験とは「その著者がどういう主張をしているのか?」を正確に読み取るだけであり、ある意味、忖度力とも言えます。
完全に忖度力ではないですけどね。
忖度するには、相手の感情や思考を裏読みしてご機嫌を取らないといけないので。
ただ、自分の意見や主張を押し殺して、迎合する点は似ています。
現代文の試験では、変に深読みしてはいけないですし、ましてや自分の解釈を混ぜたら、間違えます。
つまり、本文に書いてあることをそのまま文字通りに受け取り、答えを導き出すのです。
ある意味、ASDの人の方が文字通りに解釈するので、現代文は得意かもしれません。
しかし、現実世界では、柔軟に対応する場面が多く、相手の言動を文字通りに解釈していたら、マズイのです。
つまり、自分の解釈や予想などを入れた方が、柔軟に対応できるので、現代文試験の高得点能力は必ずしも現実世界で活きないのです。
さらに、思考力の観点から言えば、タイトルにある通り、「その人の思考過程を詳細に記したモノ」を見れば、見る人から見れば測れます。
で、共通テストの現代文試験のマーク式ではまったく思考過程が見えないのです。
現代文の国立の2次試験の記述式でも、短すぎます。
比較的、思考力を見れるのは小論文ですが、それでも短いのです。
だからこそ、論文は重要なのですね。
思考力を測るには「長い期間における、その人の思考過程(文字量)」を見なくてはいけません。
これは文字に限定するわけけじゃなく、実は話すことでも代替できます。
ですが、ジャッジが大変なので、記録が残りやすい文字にしているだけです。
ここまでの文章で、入試の国語では、文科省の方針とは異なり、「思考力なんてほぼ測れない」ということが分かりました。
試験の限界ということです。
また、思考力があると有利なのは、数学や将棋や研究など限られた分野です。
ビジネスなどになると、ただ考えているだけではダメで、実行力も問われることになります。
企画案は、創造力と思考力などで「ある程度は筋の良いモノ」が出来上がります。
ですが、それを形にするにはチームを組んだり、ちゃんと地道に実行しないといけないのです。
文科省は大学を「研究者や学者や官僚育成場」と捉えているので、思考力を強調し、実行力まで測る気がないのかもしれません。
もしくは、入試まで長年、勉強という狭い分野で頑張り抜いた点を実行力と解釈しているのかもしれません。
まぁ、この話はそれくらいにして、次は「思考力を身につけるにはどうしたらいいか?」について話していきます。
2 思考力を身につけるには?
思考力を身につける手っ取り早い方法は「一流人の思考回路・思考過程を記したモノ」を真似るか、参考にすることです。
プログラミングでも、一流人のコードは初心者とは質が違うでしょうが、一流人のコードを模写したり、解析することで、「一流人のコードの思考回路はこうなっているのか?」と把握できます。
(「理解できれば」ですが)
企画案であれば、「一流人がどういった視点から見ているのか?どういった点を重要視しているのか?」などの詳細な思考回路、思考過程を載せたモノを参考にすればいいのです。
なるべくなら一流人の方がいいですが、他人の思考回路・思考過程、つまり思考力を見たいなら「他人が書いたブログや本など」を見ればいいのです。
または「YouTubeなどの話す情報」でもいいでしょう。
僕は市販の一流人が書いた本をかなり参考にしています。
一流人が詳細に持論を述べており、思考回路・思考過程が丸わかりであり、参考になりすぎます。
ところで、一流人といえども「欠点・ツッコミどころはある」と思います。
で、「上手く反論やツッコミができるか?」はセンスやその人の経験量やクリティカルシンキング力などによるでしょう。
一流人じゃない人のツッコミはかなりピンとがずれており、的外れになりがちです。
「誰の意見が正しいか?」はビジネスなら、結果で検証するしかないでしょう。
もちろん、結果が出なくても、一部の主張は正しい場合があります。
ビジネスは単純なゲームじゃないですし、競争の激しい世界なので、儲かる方が難しいのです。
結果だけで、失敗したから過程全てを全否定するのではなく、「どれが失敗原因だったのか?」などを検証する作業が必要でしょう。
それが分かれば、改善につながり、次は成功確率が上がるかもしれないからです。
3 思考力の測り方やその他。
話を戻します。
思考力の測り方についても、付け加えて述べておきます。
思考過程を測りたければ、その人の思考回路・思考過程を詳細に細かく書いた文章、または話された会話です。
プロと素人では見ている世界が違います。
将棋にせよ、ボクシングにせよ、プロが着目している点は違います。
素人は気づけない着目点なのです。
どんな分野にせよ、プロと同じ目線で見ている、またはプロに近い、思考回路・思考過程の人なら、実力者ということになります。
ですので、思考力を測るのは試験では限界があります。
まず、一流しか正確なジャッジができません。
一流じゃない二流以下の人のジャッジだと、本当の埋もれた才能を見過ごすことになるのです。
で、一流はかなりの少数派ですし、そういう人が小論文の採点に労力の大半を注げるわけがないのです。
国語の試験、特に、ペーパー試験なんて、大した能力を測れないのです。
これがいわゆる採点者によって評価が変わってしまう恣意性というやつです。
僕は国語の試験は、「能力を測るという意味では限界がある」と見ています。
また、「エリート選抜にもなじまない」と思っています。
共通テストなら、足切りという意味合いぐらいでいいのではないでしょうか?
ですが、その足切りという機能も、ちゃんと果たせていなかったのが従来のセンター試験です。
例えば、僕のような人材は、従来のセンター試験型だと、国立大学には受かりません。
なぜなら、情報処理能力が低いからです。
情報処理能力が相当、問われているのが従来のセンター試験ですから。
情報処理能力が若干、低くても「思考力・判断力・表現力」がある人材はいます。
ちなみに、僕は耳から聴く能力は高く、2倍速でも聴けます。
(世の中には速く聴けない層がいるのです)
僕は、文字の、目から速く読み取る能力が低いのです。
いわゆる速読ができません。
まぁ何が言いたいかというと、従来のセンター国語試験なんて、6、7割ぐらいできれば御の字であり、「あまり気にしなくていいのでは?」という点です。
現代文高得点者は「こんな試験でも、9割いかないの?」とマウンティングしてくるでしょうが、気にしなくていいのです。
単に、目からの情報処理が速いだけの人なので、深く考えられて、表現できる人かどうか不明です。
ましてや奇抜なアイデアを発想したり、コミュ力があったり、実行力があるかも不明な人材です。
とはいえ、一般論でいえば、高学歴に知的分野で活躍しやすい層が集まるのですけどね。
くだらない試験内容でも、地道に努力できる人材だからです。
受験について詳しく知りたい人は以下の本がオススメです。
「受験の叡智【受験戦略・勉強法の体系書】共通テスト完全対応版」
神本と呼ばれるぐらい評価の高い本です。
(受験限定ですけどね)
僕が気に入っていたのが以下の本です。
独学派にはオススメです。
文章力を上げたい人には以下の本が断然オススメです。(名著です)
超ベストセラー「嫌われる勇気」の著者が書いた本ですから、信憑性がかなりあります。
さらに、受験について知見を深めたいなら、藤沢数希氏が書いた以下の本が断然お勧めです。
ではこの辺で。(3821文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

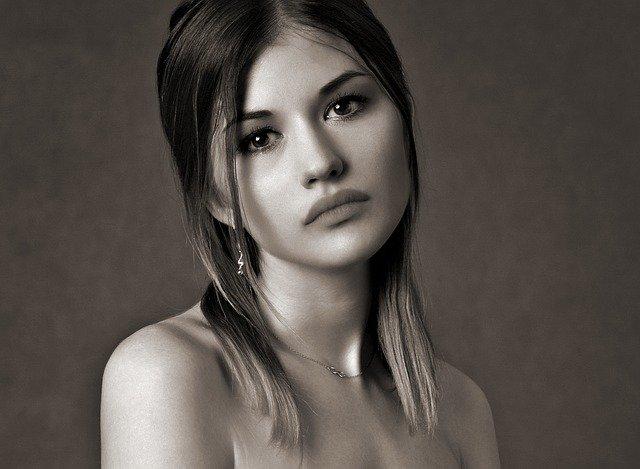







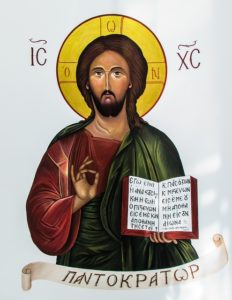
コメント