どうも、太陽です。(No149)
突然ですが、音声通話アプリGravityで、「哲学と概念の部屋」というルームがありました。
そこに最大で20人ほどは毎回集まっていて、「議論のやり方」などを教えたり、「皆で議題を決めて話し合うこと」をやっていました。
そのルームで感じたことを書きます。
また、集合知についても考察します。
興味がある人は続きを読んでください。
1 議論のやり方。
いきなりですが、「哲学と概念の部屋」で指示されていた議論のやり方は以下です。
| 1 | 主張をするなら、根拠(データやルーム内で同意が取れた場合に事実?とみなす)が必要。 (客観的主張) |
| 2 | 根拠がない主張はただの感想であり、サンプル数1かもしれず、生産的な議論ではない。 (感想とは人それぞれであり、理解はできるが、反論もできない) (主観的主張) |
| 3 | 事実?をもとに、議論を積み重ね、一般的法則らしきものを編み出す。 |
僕は、「ルーム内ではだいたい多くて20人ぐらいしかおらず、サンプル数20ぐらいで事実と言えるのか」疑問でした。
ですが、なんと以下の本には集合知として、「20人(各5人からなる4つのグループ)いて、討論すれば5180人の大集団に打ち勝てるほどの正解を導き出せる!」と書かれていました。
そして、5人のグループを4つ以上に増やしても、つまり「20人以上を集めても成績は向上せず、人員の無駄だ」ということでした。
 悩み人
悩み人ルーム内の謎のルール(ルーム内で同意をとれればとりあえず事実とみなす)は、そこまで的外れじゃなかったんだね。
また、集合知において、「皆で目的を共有するが、互いに忖度はしない」は必須条件だと以下の本では述べられています。
「そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。」
加えて、「面倒くさいから適当に判断する人」も議論に参加すべきではない、と書かれています。
あのルームでは感情的な議論になり、「だったら、もういいです」みたいな投げやりになる人がいました。
で、そういう人はルーム主に強く批判されていましたが、それが理由だったのでしょう。
また、ルーム内で「バカは議論に参加しても良いか?」が議論されていました。
本によると、「情報を持っておらず、考える能力のない人間を議論に混ぜると正解を生み出す確率を下げる」とのことでした。



実際、このルームはよく荒れており、理由はバカがたまに参入してくるからなのか。
上記に書いた「議論のやり方」すら、理解できないってことね。
「愛が大事だ!」と言ったり、「優しさはないのか?1人を詰めて、いじめているように見える」と言ったりする人がいました。
さらに、サンプル数1の感想ばかり述べたり、議論というよりも「主観的な感想ばかり言う人が多かった」です。
(議論においては「反論はOK」ですが、中には悪口としか思えない「個人攻撃をする人」もいました)
加えて、「感想を言ってはいけないのか?」もよく議論されていました。
感想は言ってもいいのですが、反論はできず、生産的ではないので、このルームでは軽視されていました。
ただ、例えば「豆腐メンタルからメンタルマッチョになった人」がいたとします。
それはサンプル数1ですが、価値ある武勇伝か経験談かもしれず、気になる人はいるでしょう。



科学的根拠のある論文は「なるべく多数に当てはまる、傾向・一般的法則を生み出したもの」に過ぎず、例外は必ず存在し、誰にでも効く薬はないよね?
どの薬が効くかわからないのだとしたら、なるべく多くの人に効く薬をまずは試し、それこそが科学的論文・一般的法則です。
「ダメだったら、違う方法を試せばいいだけの話」です。
サンプル数1か、もしくは以下の本にあるように、「N-1の極端な経験談でもマーケティングに応用できる」という本も出ています。
経験談はその背景にあるストーリーが重要であり、そのストーリーに中に一般的法則につながるヒントが隠されているかもしれません。
「たった一人の分析から事業は成長する 実践顧客起点マーケティング」



帯に謳い文句として「1000人より1人の顧客を知ればいい」と書かれているね。
ところで、あのルームの主は職業がデータサイエンティストらしいので、「そこそこ合理的なことを暗にやっていた」のです。
(主の説明が下手か、理解力が低い人がいて、よく荒れていましたが。最近はある理由で、そのルームにはまったく出入りしていません)
2 ルームにいた、ある人の主張。
ここで、ルームにいた、ある人の主張を書きます。
(議論が行われていました)
| ・ | マイノリティーによる「言葉狩りやクレーム」によって、マジョリティーの権利が脅かされる。 |
| ・ | 「お母さん食堂」という偏見のなさそうな言葉でも、イチャモンをつける連中がいる。 で、企業側が対応し、世の中から消える怖さ。 |
| ・ | そのうちに、「おじさん・おばさん」という言葉すら禁句になり、権力者や偉い立場にいる人は「言葉選び」にかなり注意しないといけなくなりそう。 そもそもどんな失言?でもいちゃもんをつけるのが「モンスタークレーマー」なので、抵抗は無理。 |
| ・ | ある人は失言癖があり、自分が仮に出世したら、「言葉狩りに遭い、失脚させられそうだ」と恐怖。 |
| ・ | マイノリティーこそ、タフになり、些細なことで傷つかないようにすべきだ。 また、企業側も毅然とした対応をすべき。 |
| ・ | お母さん食堂が「ファミマル」という新ブランド名に変わったように、マイノリティーによりイチャモンをつけられ、「名称が変更される用語」が今後も増えていきそう。 だが、「古い名称がそんなに消えていっていいのか?」と問題提起。 (新しい用語に変わるのだが、「それもいいのか?」と疑問) |
ちなみに、お母さん食堂の事例は以下の記事を読んでください。
https://president.jp/articles/-/51361?page=1
「お母さん食堂」は本当にアウトなのか…モンスター消費者の”言葉狩り”が止まらないワケ
ある人が個人レベルで対応するのはかなり難しいです。
できるとしたら、力をつけてから、企業側に「マイノリティーのイチャモンに屈するな!」と訴えて回ることです。
もしくは、100万人レベルのYouTuberになり、影響力をつけることも考えられます。
さらに、「メディアを作り、影響力をつけて発信するか」でしょう。



ある人が実際にやっているのはGravity内での些細な発信と、「これからSNS系のアプリを作り、そこで発信する」ということか。
マイノリティーの権利も大事ですが、それが行き過ぎると「マジョリティーの権利の侵害や窮屈さ」につながります。



簡単にいえば、「些細なことで傷つく側が悪いのか(敏感)、発信する側が注意しなければならないのか」ということか。
マイノリティーは本来なら「弱者の側」でした。
ですが、現代ではマイノリティーが過剰に?権利を主張することで、逆に「マジョリティーに窮屈さや我慢を強いている」という逆転の現象が起きています。



「マイノリティーの権利はどこまで認められるべきなのか?」という問題提起だね。
また、「マイノリティーを尊重する」ということは多様性の問題でもあります。
多様性は「寝る脳は風邪をひかない」という本によれば、多様な集団がいることで集合知がうまく発揮されることも稀にありますが、「ほとんど起きない」とのこと。
加えて、多様性の役割は外部撹乱の際に、頑強性を生み出すことです。
逆に言うと、「有事にならなければ意味がない」ということです。
「いつかの備え」のときのために「多様性は残されている」に過ぎず、資金力が重要になります。



つまり、貧乏な国は多様性などと言っておられず、選択と集中で限りある資源を有効活用するしかないんだね。
また、ある人は「受け手のアップデート」を盛んに掲げていますが(些細なことで傷つく側が悪い)、変わりやすいのは自分自身です。
変えにくいのは他人です。
ですから、「受け手のアップデート」の啓蒙活動もかまわないですが、効率性などで言えば、発信側が注意するのが最善になります。
「切り取り」も横行していますが、発言にかなり慎重になり、変に切り取られないように言葉を選ぶしかありません。
3 男女脳について。
ここで、男女脳について書いていきます。
ルーム内において、「男女脳の違いがある!」と主張する人もいれば、「そんなものはない!男女において性差はない!」と主張する人もいました。
現実は「どうやら男女に違いはある」とのこと。
男性の15%に女性脳がいて(さらにやや女性脳が15%いて、全体の30%が女性脳)、女性の10%に男性脳がいるとのことです。
以下の記事で、男女脳の判定ができます。
https://diamond.jp/articles/-/63354?page=2
8個の質問で脳のタイプがわかる!
あなたは男性脳?それとも女性脳?
僕の結果は8問中6問が男性脳でした。
さらに、以下の記事の判定テストでは14問中、Aが14問と、完全なる男性脳でした。
話を戻します。
科学的な正しさでいえば、「男女に違いはある」のですが、一般受けするのは「男女に違いはない!」です。
「科学的な正しさ」と「社会的な正しさ」は異なります。



人間は理性よりも感情で動く人が多い。
だからこそ科学的真実よりも社会的真実が受け入れられる。
そして、世間が科学的真実を受け付けなければ社会から拒絶されるんだね。
ところで、1800年代は感情的な人間が多かったです。
しかし、1900年代になると感情的人間はかなり減りました。
さらに1980年代以降はまた感情的な人間が増えました。
加えて、2007年以降は1800年代よりもはるかに感情的な人間が増えた、とのこと。



つまり、科学的真実よりも社会的真実の方を重視する人間が増えたので、メディアも対応し、「エビデンスに基づく報道がしづらくなっている」ってことか。
遺伝子組み換え作物でいえば、科学者の88%は「遺伝子組み換え作物は健康に害がなく食してもよい」と答えるが、一般人では37%しか肯定的に答えません。



他にも「テレビを近くで観ると目が悪くなる」という説が世間ではまかり通っているけど、科学的には無根拠な迷信だね。
以上、集合知やルーム内での「議論のやり取り」について書いてきましたが、参考になる箇所はあったでしょうか?
僕は知的な会話ができる相手がほしいので、「こういうルームの存在はありがたい」と思っています。
(ですが、このルームに僕は今は行っていません。理由は省略)
最後に、「哲学と概念の部屋」ではよく会話者同士が揉めていました。
それは以下の記事にあるように、「科学的思考と日本人が相性が悪いからかもしれないなぁ」と思うようになりました。
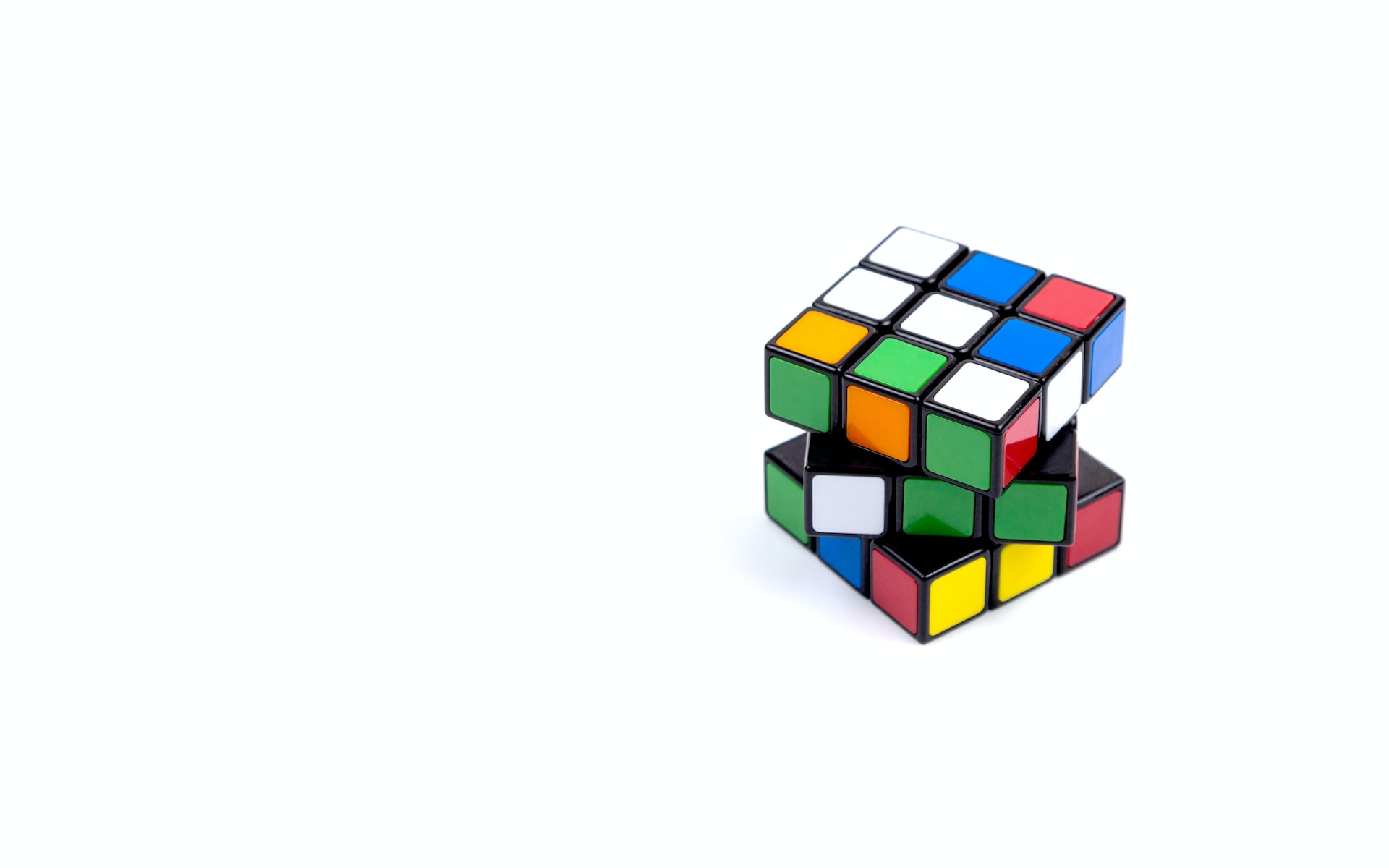
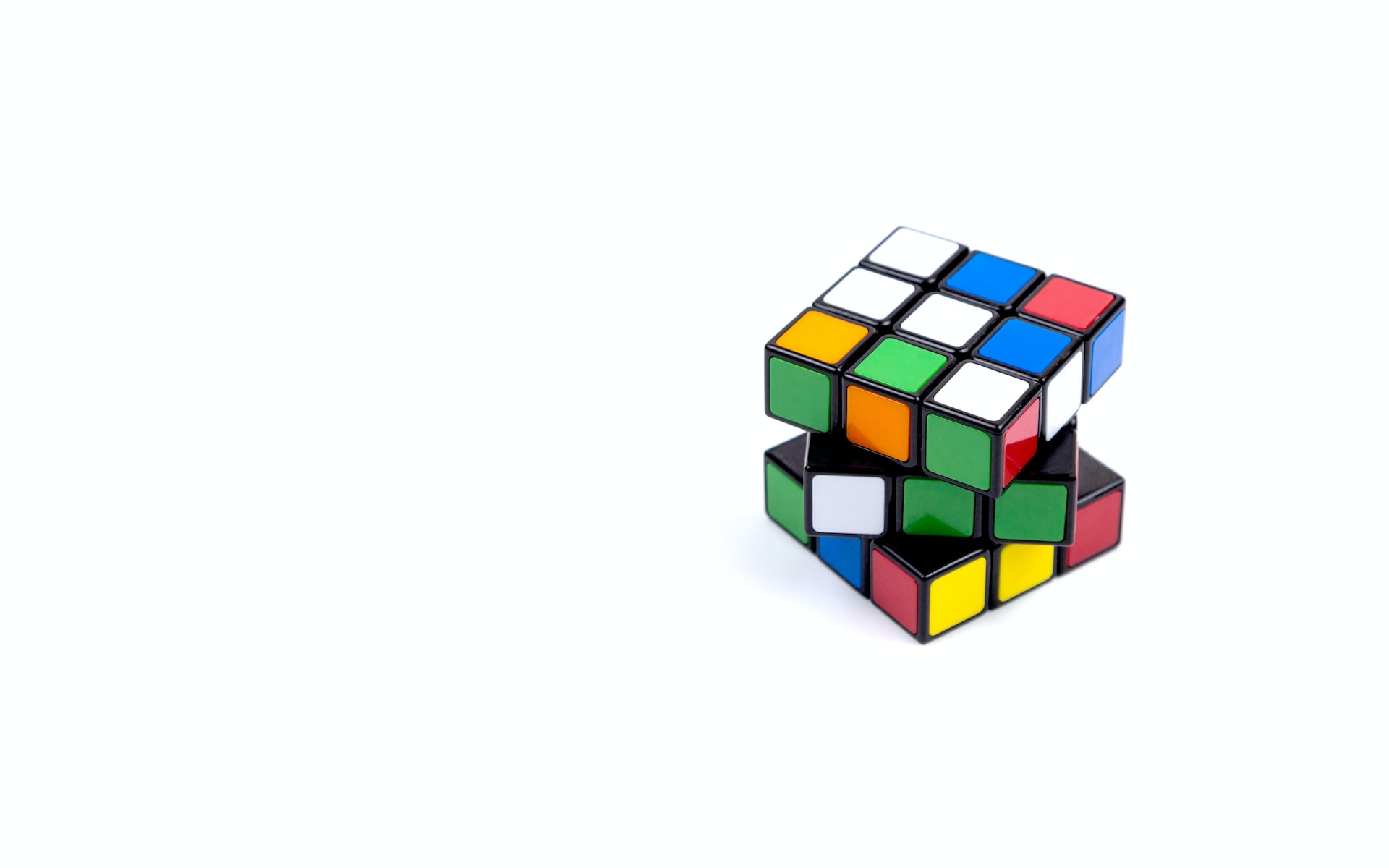
ではこの辺で。(4017文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。








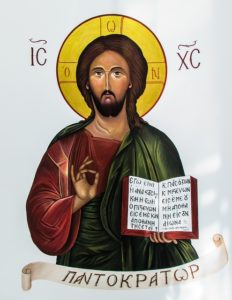

コメント