どうも、太陽です。(No94)
突然ですが、「友達がそこまでいらないのでは?」という友達論を展開していきます。
メンタリストDaiGoのYouTube動画を4つを紹介しています。
それと僕の記事をプラスして、僕の主張を書いています。
最後に、林修氏の主張も追加しています。
興味がある人は、続きをお読みください。
1 メンタリストDaiGoの動画の紹介1 「人見知りでも友達を作れる方法とは」
いきなりですが、「人見知りでも友達を作れる方法とは」というタイトルです。
以下の動画を貼ります。
https://www.youtube.com/watch?v=C4PVM6JnveY
メンタリストDaiGoによると「友達は必要」という研究結果が出たそうです。
「友達を作ることのポジティブさや有用さ」が語られています。
詳しくは動画を見てください。
2 メンタリストDaiGoの動画の紹介2 「実際は中身のないやつの見抜き方」
以下の動画を貼ります。
「実際は中身のないやつの見抜き方」というタイトルです。
https://www.youtube.com/watch?v=ZneXKyKJCTI
「人脈があると言いつつ、実際はない人」、または「実力があると言うのにまったく実力がない人」、つまり口だけの人の見抜き方を紹介しています。
また、5つのコミュ力を上げる方法を紹介しています。
チェックリストや判定ができます。
僕は動画を見て「ほんとうに、自己評価はあてにならないな」と思いました。
ほとんどの人が「自分は平均より上だ」と思っていますしね。
自信過剰になっていないと、鬱病になるのです。
そして自信満々な人はかなり危険です。
むしろ、「慎重だったり、自己評価が厳し目の人のほうが将来、伸びるし、信頼しやすい」と思います。
詳しくは動画を見てください。
3 メンタリストDaiGoの動画の紹介3「無視すべき親の意見」
以下の動画を貼ります。
「無視すべき親の意見」というタイトルです。
https://www.youtube.com/watch?v=n3TAFLGez_M
親の意見で、無視したほうがいい意見があり、それは人間関係についてです。
詳しくは動画を見てください。
友達付き合いについて、深く語られています。
4 メンタリストDaiGoの動画の紹介4 「友達むしろ減らして幸せに」
以下の動画を貼ります。
「友達むしろ減らして幸せに」というタイトルです。
https://www.youtube.com/watch?v=Ed-T7lKVYBA
友達は数は量じゃなく、質です。
で、「まず量を大事にし、そこから質を追い求めるべきだ」と言いますが、「それは疲れる」とメンタリストDaiGoは言います。
「いい友達関係とは何か?」が語られています。
詳しくは動画を見てください。
5 記事からの引用。
以下の記事「天才論「凡人が天才を殺すことがある理由 どう社会から「天才」を守るか」について」から、引用します。

金融資本(お金)も大事ですが、それだけでなく、オピニオンとエグジットを行使するには、人的資本(汎用性の高いスキルや知識)と社会資本(信用や評判など)を厚くすることが大事です。
略。
問題解決のアプローチには大きく、「ランダム(直観によって回答を得る」「ヒューリスティック(経験則によって回答を得る」「オプティマル(論理によって回答を得る)」の3つがあります。
これはそれぞれ、直感や勘を用いる「ランダム」は「アート」に、手間をかけずにいい線を行く答えを求める「ヒューリスティック」は「クラフト」に、分析と論理によって最適解を求めようという「オプティマル」は「サイエンス」にそれぞれ該当します。
過去に類似した事例があるのであれば、「クラフト」は有効でしたが、不確実性が高い問いなら、クラフトの経験則は当てにならず、「アート」か「サイエンス」の出番になり、「その2つは年齢は関係ない」ということになります。
それどころか、「大胆な直感」や「緻密な分析・論理」は「若い人の方が得意だ」ということが分かっています。
将棋の藤井7段の活躍が物語っています。
また、知性と年齢については、「流動性知能」と「結晶性知能」の話が参考になるでしょう。
「流動性知能」とは、推論、思考、暗記、計算などの、いわゆる「受験に用いられる知能」のことであり、分析と論理に基づいて判断する類の知能(サイエンス)といえます。
一方、「結晶性知能」とは、知識や知恵、経験知、判断力など、「経験とともに蓄積される知能」であり、経験則や蓄積した知識に基づいて問題解決をする類の知能(クラフト)といえます。
ここで重要なのが、2つの知能ではピークに達する年齢が大きく異なり、「流動性知能」のピークは20歳前後にあり、加齢とともに大きく減衰していき、一方の「結晶性知能」は成人後も高まり続け、60歳前後でピークを迎えるという点です。
これがかつての「定常社会」において、60歳前後の長老が大きな発言権を持ち、尊敬される理由だったのです。
このような社会では新しい問題は「流動性知能」に優れる若者たちが向き合い、直感の通用しない複雑な問題については「過去の経験知を蓄積した長老が向き合う」という形で役割分担し、組織やコミュニティを維持していました。
ですが、現在の社会の変化は極めて早いので、経験則が知恵になるか、不透明な時代になったのです。
ブラック・スワンのような「ごく稀にしか発生しない大きな問題」についての経験は長く生きてきた長老が独占していましたが、今はグーグルなどで簡単に調べられます。
(年長者のデータベースとしての価値がなくなったのです) 以上、ここまで。
この内容がどういう風につながるかは、続きをお読み下さい。
6 僕の意見。
基本的に仕事にせよ何にせよ、「問題解決をすることの連続」が人生というものです。
「問題解決をする場合、人はどうするか?」でその人の性格などの傾向が丸わかりとなります。
エニアグラムで分類すると、「以下になる」と思います。
エニアグラムでいうタイプ6(堅実家)は、問題解決の際に、「人に聞く、アドバイスを求めること」を頻繁にします。
タイプ5(研究者)の場合、本を読んだり、ネットで調べまくるでしょう。
(さらに、分析と論理であり、サイエンス重視派です)
タイプ8(統率者)はあまり調べず、どんどん行動し、人の意見もあまり聞かず、突っ走り、痛い目を見てから気づくことを繰り返すでしょう。
(行動力は抜群にあるのです。そして「他人に命令されたり、干渉されるのが大嫌いな人たち」です)
タイプ4(芸術家)は、直感や勘で行動するでしょう。
(アートで動くということです)
何かの問題(その人にとって不確実で、今まで経験したことがない事例)に直面したとき、人のエニアグラムの分類、または知識や学習によって修正した人は、そのやり方で問題解決を図ろうとします。
メンタリストDaiGoは知識量豊富であり、コミュニケーションの問題なら、ほとんど人の手を借りずに、問題解決できてしまうでしょう。
「知識量が豊富であり、論理や分析手法も得意である」ということは、サイエンスの手法で問題解決ができてしまいます。
それは時に、経験則や直感や勘を超えることもあります。
(AmazonやGoogleはデータ分析の会社です)
加えて、「経験則で今後、問題解決の多くをしようとする人はオワコンだ」と僕は思っています。
経験則がピークになる結晶性知能は60歳ですよ。
経験則ということはかなり歳を取らないといけないですし、経験の多様性や質も大事になってきますし、そもそも「経験則が流用できない事例が増えてくる」と思うからです。
となれば、基本路線は直感や勘(これも経験則の積み重ねとデータ量により、磨かれるのだが)や論理と分析手法が良いことになります。
話を戻しますが、メンタリストDaiGoの場合、金融資本(お金)が豊富にあり、人的資本(稼ぐ力)もあり、社会資本(人脈や評判など)もある程度、あります。
つまり、「こういう人は有利に生きられる」ということです。
他人の助けを借りる必要性が弱くなるのです。
以下のお金の記事でも述べました。
ところで、人生は「問題解決の連続」だとすれば、「友達がなぜ必要なのか?」と言ったら、問題解決の際に助けになる面が大きいからでしょう。
もちろん、精神的な満足度も高めますよ。
仕事上の関係だけの人というのは「浅い付き合い」であり、問題解決の際にあまり心底、助けてくれないんですよね。
こういう時、頼りにになるのがプライベートの友達(社会資本)、または金融資本(金)、自分の問題解決力(人的資本であり、アート、クラフト、サイエンスにせよ)ということになります。
そして、「友達がかなり必要だ」と強調する人ほど、自身の生きる力が弱いのです。
地方のマイルドヤンキーは社会資本(人脈など。友達付き合い)が豊富です。
金融資本と人的資本の弱さを、友達どうしの結束で補っているのです。
で、ですよ。
友達がそこまで必要ないという人は、「自力で生きていける部分が強い」ということであり、「生きる力が強い人」なのです。
だいたいの問題解決も自力ででき、人に頼ることが少なくなります。
これもある意味、理想郷じゃないでしょうか?
そして、世の中の困りごとや悩みの問題解決法なんて、だいたいは本やネットに載っています。
(もちろん、不確実で前例があまりない事例もたくさんあります)
そう考えると、本を大量に読める人は有利なのです。
(僕も正直、だいたいのことは本やネットで調べて、あとは論理と分析手法で解決すれば「事足りるかな」と思っています。直感や勘も大事にしますけどね。経験則だけが脆弱であり、他人の経験を聞いたり、本を読んで疑似体験して補っています)
結論として「友達ってそんなに必要なくね?」というのが僕が思う意見です。
「なるべく自力でできることを増やし、仕方ない時は金の力で解決した方が生きやすいですよね?」って話です。
僕のブログも、読者の皆さんの「問題解決」や「意思決定の際の判断軸」に「かなり参考になる」と思っています。
活用できる点は活用してください。
7 林修の友達論。
以下の動画を貼ります。
「【林修】いま将来の方向性で悩んでいるひとが多すぎる「自分の方向性をつかむために必要なこと」」というタイトルです。
https://www.youtube.com/watch?v=_0WmirKRATM
簡単に要約します。
林修氏は「友達が少ないことが自慢だ」と言っています。
本当に気の合う、相性が良い人が世の中にそんなにいるわけがなく、「友達が多いということはどこかで合わせている可能性が高い」といいます。
仮に、相性がいい友達がいて、それならば楽しいですが、「同じ話を何回もしている」場合が多く、例えば「その話、もう38回くらいしているだろ」という事例が多いと言います。
「そういう友達の付き合いを減らしても問題ないだろう」と林修氏は言います。以上、ここまで。
友達と「生産性ない、ムダな時間を長く共有している」とすれば、非効率な人生を送っているのかもしれません。
もちろん、孤独が嫌で「誰かと一緒にいたい」という寂しさが嫌いな人たちは友達付き合いは必須ですけどね。。。
「君に友だちはいらない」という故瀧本哲史氏の本もありましたね。
ではこの辺で。(4774文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。




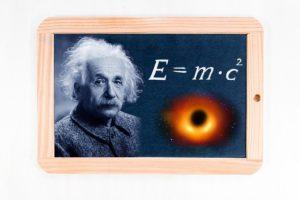
コメント