どうも、太陽です。(No165)
突然ですが、余計なお世話をする人達っていますよね?
自分たちは「親切のつもり」でやっているのでしょう。
だけど、相手からしたら求めていないのに勝手に助言されたりするから、「ウザい!」と思っている人達も「多いんだろうなぁ」と予測します。
こういう「親切のつもりで余計なお世話をするタイプ」は以下の記事でも登場しているエニアグラムでいえばタイプ2が多そうです。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e3a315a69b4dcb0d7bd80607e76b092547bbf27f
もう1度言います。「悪いことをするのは、お母さんタイプ(エニアグラムでいうところのタイプ2)です」
ですが、今回の記事では余計なお世話ではあるけど、実は的確な余計なお世話の件です。
つまり、その人にとってはかなり必要な助言や支援をしてくれる人達について考察していきます。
興味がある人は続きを読んでください。
1 的確な余計なお世話とは?
いきなりですが、的確な余計なお世話の例として、例えば、ひかりん@婚活阿修羅さんの以下のツイートがあります。
「恋愛経験ゼロの適齢期のハイスペ男子が美人地雷女性と幸せそうに成婚していくのを見送るのが本当につらい。
本人が幸せそうなの止めるわけにもいかないし…。
でもその子は無理でしょ。
明らかにATM枠。
数年後にやっぱり好きじゃないと無理とか言われて離婚されて養育費払うところまで見えてつらい…」
「婚活男子に質問です。私は止めるべきでしょうか?
止めるべき 28.8%。
余計なお世話 30.4%。
回答だけ見る 40.9%。
3576票。最終結果。」
いろいろな意見がありましたが、止めるべきと余計なお世話が拮抗しています。
止めるべき派は「止めるべきだと思うけど、それで止まる人はほぼいないから、実質見送りになる」という主張がありました。
余計なお世話派は「確証があるわけじゃないし、人に言われて分かるなら本人も分かっているだろうし、一緒に生活するうちに本当の家族になるかもしれないから、可能性まで奪うのは良くないのでは?」もありました。
折衷案として、「自分の資産を守り抜く方法だけ教えて、それで伝わらなかったら、トラブったときに相談に乗って距離を置きながら自分で解決できる法的な方法だけ伝える つまり、「口は出すが首はツッコまない」」というのもありました。
ひかりんさんは長年、婚活コンサルをしてきた経験が豊富なので、先を見通す力が高くて、結論が分かってしまうのです。
ですが、「残酷な真実を本人に伝えても、それで本人が意見を変えるか?」は不明です。
で、余計なお世話になるし、感謝もされないから、悩むところなのでしょう。
まぁある意味、こういう余計なお世話で悩む人は根はいい人だと思います。
どうでもいい人や他人なら、放っておきますから。
どうでもいい人が不幸になろうが普通は気にならないのです。
ただし、身内や顧客や友達だと、「余計なお世話をすべきか?」問題が発生します。
どうでもいい人じゃないからです。
ここで残酷な真実を伝えるのは勇気がいります。
相手は落ち込む可能性が大ですし、もしかしたら関係が悪くなるかもしれません。
だったら、放っておくほうが自分にとっては精神的にも労力的にも楽です。
また、ある人と議論になった話があります。
先回りして事前に余計なお世話(知識を教えるやサポートなど)をするべきか、それともしないで失敗させて学ばせて自律性や主体性をもたせるべきか、というモノです。
その人は、「聞かれたら、答えるよ」と言っていて、基本的に相手の主体性に任せる派でした。
僕は致命的な点については、事前に先回りして教えてしまう派です。
なぜなら、質問できるのは事前に知っていることだけであり、知らないことは相手に聞けないからです。
そして、致命的なダメージを食らうことを放っておくと、相手は後で苦労します。
しかも相手はそれを知らないから質問できない構造になっています。
ですから、僕は事前に教えてしまいます。
これはひかりんさんのツイートの内容と似ている点です。
「地雷嫁であり、ATM扱いであり、後で離婚されて養育費を払わされる」という話はある意味、致命的です。
これに対し、聞かれたら答えるよ派は、そんなことを、地雷嫁と結婚したハイスペ男子は知らないのですから、「質問しようがなく、野放しにする」ということになります。
これはある意味、残酷であり、アドラー心理学を学んだ課題の分離、つまり他人の課題に極力踏み込まない態度の人です。
僕だったら、こういう致命的な点に対しては、どうでも良くない人に対しては、丁寧に相手に最大限配慮して伝えると思います。
そして、伝えて、あとは本人次第でしょう。
しかも、この点に関しては、伝えるのはリスクがあります。
なぜなら、どんなにその分野で経験を積んでいても100%悪い結果になるという確証はないからです。
上手くいく可能性もあり、仮に相手が断固、意思を貫いて、その結果、上手くいった場合が困ります。
「あのときのアドバイスは聞かなくて良かったよ。大きな余計なお世話だったよ」という結末になりますから。
リスクを冒して、相手にわざわざ忠告するわけで、楽をしたいのなら、相手を放っておくのが一番いいのです。
「聞かれたら、答えるよ」派は、相手の主体性を尊重しているようにみえて、リスクも負っていないし、かなり楽をしているのです。
まぁ子育てという面で言えば、主体性を育てるためにも、自分から進んで質問しまくり、難題を突破する人材になってもらいたいですよね?
ですが、致命的な失敗の場合、かなり痛い目を見て学ぶことになります。
そういう経験も必要でしょうが、何度も味わうべきものなのでしょうか?
これは非常に難しいテーマであり、「地獄をみた人間は強い」のは僕の経験則からよく分かっています。
致命的な失敗を何度も冒してきたからこそ、今では失敗を避けるのが上手くなりました。
ですが、僕のような人生を「他の人が学ぶ必要があるのか?」不明です。
わざわざ遠回りして、こんな教訓を学んでいたら、人生の絶頂期が終わってしまいます。
「的確な余計なお世話をするべきかどうか?」は悩ましい問題です。
また、以下の記事にあるように、課題の分離と無責任の違いがわからなくて、モヤモヤしている人がいました。
難しいテーマですが、課題の分離を濫用する人って、「楽をかなりしたい人」に見えてしまいます。
少なくともギバーではなさそうです。
あとは、相手の望まない手助けをすると数週間持続する高いストレスを与えるとのことなので、要注意です。
https://nazology.net/archives/151898
相手の望まない手助けは数週間持続する高いストレスを与える!
2 遺伝率の話。
ここで少し、話がずれますが、興味深い話ですのでついてきてください。
スポーツの遺伝率は8.5割で、数学も8.5割、執筆は8.1割、音楽は9割、チェスは5割なので、将棋も似たようなものでしょう。
遺伝率が高いと、才能がほとんどで「自分には無理だ!」と諦める人は多そうです。
ですが、遺伝率の実態を知ったら、多少は認識が変わるかもしれません。
遺伝率はどうやら、100点満点でスコア化すると、以下になります。
例えば、数学の場合、できる人とできない人の差が激しいのでバラツキを大きくとると、10点〜90点で同じ環境下で努力すると仮定して、その差の80点は遺伝率で決まるというものです。
数学なら遺伝率は8.5割なので、その差の80点のうち、68点は遺伝で決まり、努力の余地は12点となります。
つまり、遺伝率は8.5割から、6.8割に低下するのです。
では、トークスキルはどうでしょうか?
コミュ力は「努力6割、遺伝3割、才能1割」という検索記事を見かけました。
で、「遺伝と才能って違うの?」と疑問がありますがまぁいいでしょう。
(トークスキルの遺伝率は調べられていません)
まぁトークスキルを仮に30点〜80点の範囲とすると(コミュ力は皆、日常でやってるのでバラツキが小さい)、50点の差は遺伝率3割とすると、15点が遺伝、努力の余地は35点になります。
つまり、遺伝率3割から、さらに低下して1.5割が遺伝率になります。
これらは母集団を考慮して測った遺伝率です。
僕はこの話をGravityの人に聞いたのですが、真相は正直、不明ですが、ある程度は納得がいく理屈です。
以下の本を読んで調べてみます。
ちなみに、以前は遺伝率6割ということは、100点のスコアなら「60点の影響度(寄与度?)がある」と考えていました。
遺伝率6割なら、100点満点中60点が遺伝率で、「その他(共有環境、非共有環境)が40点」という解釈だったのです。
%で示されていますし、「百分率に計算できる」と直感的に思い、あまり疑っていませんでした。
ですが、Gravityの人も以前は僕と同じ解釈だったのですが、今は以下の本を読んで、上記のような解釈に変わったそうです。
また、以下の本も積読しています。
「生まれが9割の世界をどう生きるか 遺伝と環境による不平等な現実を生き抜く処方箋」
3 客観視力とコミュニケーション力。
遺伝の話から、客観視力とコミュニケーション力に移ります。
(話が変わりますが、ついてきてください)
「客観視力や現実認識力・把握力(以後、客観視力に統一)がコミュ力と関係があるのか?」とふと考えました。
結論として、客観視力が高ければ、自分のコミュ力の高低について正確に把握していることになります。
ですが、「知っているとできるは別もの」です。
客観視力が高い人は、正確に把握していて知っています。
ですが、有能で実行しているかは別なのです。
逆に、客観視力が低くても、勘違いして、猛烈に努力し、行動力で成功する人はいます。
正確な事実らしきことを言うのが学者や研究者です。
正確な事実らしきことより実行が起業家です。
まぁ理想は正確に把握しつつ、実行もできたら、失敗が減り、効率がいいはずです。
ですが、正確な事実の把握はときに萎縮を生じさせます。
どうせ失敗するからやらないになるのです。
ときに勘違いで突破し、飛躍する人もいます。
認知の歪みがある人でも、失敗しまくりながら、突破する人もいます。
「何が言いたいか?」というと、以下になります。
遺伝率もそうですが、遺伝率が見かけ上高くて、「努力の余地が小さい」と思っていても、「メンタルと努力で克服や突破できる可能性は残る」ということです。
しかも、遺伝率は実際はもっと低いらしいのです。
そして、「的確な余計なお世話をすべきか?」問題ですが、100人に1人か、1000人に1人か分かりませんけども、稀に勘違い力で突破してしまう人がいます。
ですから、「的確な余計なお世話の指摘ぐらいはしてもいい」と思いますが、稀に突破する人がいるのです。
で、「そういう人の可能性まで潰すのは良くないかもしれない」ということです。
大谷翔平選手の米国での二刀流は大成功しました。
まぁあれは日本でも成功していたので、実績が既にあり、確率的にはアメリカでも通用するのが「50%ぐらいはあった」と感じます。
僕の言う的確な余計なお世話の指摘は、的中率として「だいたい80%以上はあるもの」を想定しています。
20%ぐらいは外れるのだとしたら、指摘だけして、相手に一任するのもありかもしれません。
最後に、再度、遺伝の本を紹介して終わりとします。
「生まれが9割の世界をどう生きるか 遺伝と環境による不平等な現実を生き抜く処方箋」
自分用のメモとして、今回の僕の記事と似た内容の記事を残しておきます。
https://shuchi.php.co.jp/article/9813
「他人を傷つけない人」はやさしいのか? 配慮の後ろに隠されたホンネ
ではこの辺で。(4383文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

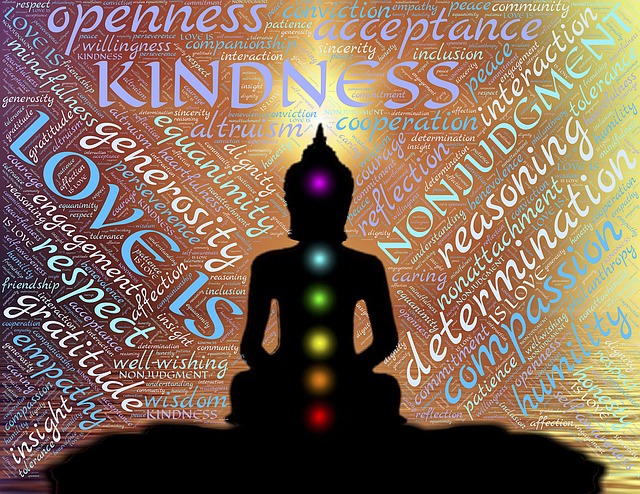




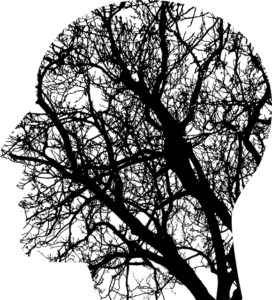
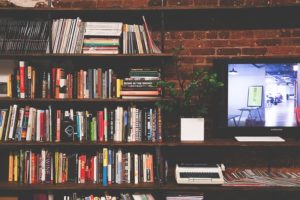


コメント