どうも、太陽です。(No70)
突然ですが、「現代文、小論文が危険とは、どういう意味?」とタイトルを読んだ人は思ったかもしれません。
僕は、「現代文は欠陥がある試験である」と考えており、「その欠陥を暴きたい」と思います。
小論文は現代文よりはマシなのですが、それでも欠陥があり、それも暴きます。
国語の試験は両方とも欠陥があり、「限界がある」というテーマです。
また、本番の現代文試験に欠陥があるとしたら、「普段の現代文授業は意味がないのか?」と思われるかもしれませんが、「そこまででもない」と思います。
その理由について詳しく書くので、興味がある人は続きをお読みください。
1 現代文の試験の欠陥とは?
いきなりですが、現代文(小説も含む)で言えば、「わざと難解な文章を選び、しかも全文ではなく、一部を切り取った文章であり、さらに、巧妙な選択肢で平均点を下げる調整試験」と言うことができます。
日本語であれば、普通は分かりやすく書けば、ほとんどの人は理解できるわけであり、わざわざ難解に書く理由は普通はないのですが、落とす試験の目的上そうなっています。
難解な文章を読み解くスキルは、限られるでしょう。
そして、難解な文章は、高尚なわかりにくい表現を使って難解に見せているだけです。
で、大抵においては言っていることは大したことないことが多いと感じます。
(もちろん哲学やアインシュタインの相対性理論など、元々難しいものもあります。それらはいくら分かりやすく書いても難しくなってしまいます)
マークシート方式の現代文の試験の弱点は「とりあえずの答えを出して後は深く考えない癖」や「選択肢以外の可能性を考えない癖」など、現代社会の答えがない世界を生き抜く上で、不利な性癖を育てている可能性があることですね。
以上が、現代文の試験の欠陥です。
2 現代文の試験の目的と小論文・論文の特性について
次に、現代文の試験の目的は「著者の主張を正確に理解できているか、または情報処理が速く、理解できているか」です。
これが現代文の試験の特徴だとすれば、試験の出題されている著者の解釈以上の解釈をしてはいけないことになります。
「著者の解釈以上の解釈をしたら、正確に理解できていない」とされ、点数が上がりません。
この欠陥を補おうとしたのが、小論文です。
小論文は要約で、「著者の主張を正確に理解できているか?」を把握できます。
次に、著者の解釈以上の解釈をしているのか?を、文章力や論理性も見つつ、受験生の発信力(アウトプット)まで見れるのです。
これで、「小論文に分がある」と思いましたが、そうは簡単にはいきません。
その理由を述べる前に、以下の主張を書いておきます。
論文(とアウトプットの成果物)の価値とは、僕は「新規性」と「重要度」だと思っています。
「新規性」とは独創的であり、従来、誰も発信していなかった主張を述べることです。
「重要度」とは「新規性は少なくても、人生や世の中において役立つ、実用性が高い主張は価値がある」という視点です。
そもそも本質論を言えば、本当に重要なことなど、過去の偉人がほとんど言っています。
あとは、組み合わせ方法に自由度が残されているだけであり、完全なる新規性は難しいのです。
ビジネス書でも「知っている」と大半の人が思う内容は多いのですが、「それを愚直に活用しているか」は別問題です。
重要で役立つことは「新規性が薄れがち」ですが、そういう主張は役立つのです。
さて、論文(とアウトプットの成果物)の価値は、「新規性」と「重要度」と書きましたが、今は「新規性」に重きを置かれているようです。
ビジネス書の場合ですが、ビジネスの骨格となる理論自体は、もはや古典的な理論でほぼカバーできるし、実用性もあります。
ですが、経営学者やビジネス書著者は、わざわざ新規性を求めて、読者の欲求を満たそうとします。
3 重要な話
さらに、ここで重要なことを述べます。
人の価値観はそれぞれであり、自分が興味ないと思う分野は軽視するか、「価値」を見出さないのが人間です。
僕の文章でいえば、ビジネスや自己啓発に興味がない人は「つまらない、陳腐なもの」に見えます。
特に、教養派の人は、僕の文章など興味がかなり薄れ、価値を見出さないでしょう。
しかし、ある人の興味と価値と「重要度」は違います。
僕の本は、「新規性」もなるべく追求しようとしてますが、「重要度」には大変、価値があると思っています。
さらに言えば、「情報の整理」(キュレーション)という価値を、ほとんどの人が軽視しているように思えてなりません。
「他の人の意見の受け売りだ!」や「独自の主張がない!」と、僕の文章を読んでいる人は思うかもしれません。
ですが、膨大な情報を読んで選んで、体系化し、整理するということの大変さと価値が分かっていないように思うのです。
ビジネス書でいえば「経営戦略全史」という本は、著者の独自の主張は一部ですが、大量の情報を整理し、体系化したことに非常に価値がありました。
体系化され、整理された情報は頭の中が整理され、自分のアウトプットの参考になりやすいですし、どこに独自の主張をする盲点があるかなど、を見つけやすくなります。
僕の記事「ビジネス書の目利きによる日本の教育改革本」は、ビジネス書でいえば「経営戦略全史」に近い位置づけです。
つまり、情報の整理、体系化路線&人生の全体図、俯瞰図です。
「この価値もわからない、独自の主張がない」(一部は僕も独自の主張を入れていますよ)と、一刀両断する人がいます。
ちなみに、漫画版の「経営戦略全史」もあります。
2冊とも名著です。
4 小論文の危険性と改善案
さて、ここで話を「小論文」に戻しますが、「小論文」の危険性は、「採点者の解釈以上の主張をすると、評価されないこと」です。
いわば、採点者の恣意性に左右されるのです。
例えば、大学院生の中には、「指導教官の主張に沿わないことを主張すると、減点されるか、評価されないから、指導教官の言うことに合わせよう」とか言う人もいます。
つまり、価値が分からない指導教官や採点者に、小論文や論文(やアウトプットの成果物)を評価させると、その人は評価されないかもしれないのです。
ここに非常に、小論文という試験の危険性を感じます。
現代文もまったくダメですが(特にマーク式)、小論文でさえ、このように欠陥があります。
「現代文、小論文という試験はどのようなやり方が理想なのか?難しい」と言えます。
そもそも試験という性質と合っていないのでは?とも感じます。
小論文や論文の場合、評価基準をある程度網羅して、たくさんの人数に見せることが大事です。
1人の採点者に任せたら、採点者が無能な場合、本来の実力者がはじかれることになります。
その画期的な現代文、小論文の画期的な改善案が「日本論文プラットフォーム」という提案ですが、詳しくは省略します。
5 普段の現代文の授業は意味ないのか論。
最後に、「普段の現代文の従業は意味ないのか論」について回答を述べます。
僕は「意味がある程度ある」と思っています。
というのは、共通テストの国語試験のように完全に「落とす」ための試験じゃないからです。
言わば、国語の基礎力(漢字や四字熟語や文章に慣れるなど)を身につけるのが、「普段の現代文の授業だ」と言えます。
ただし、「どの教材を用いているか?」問題はあります。
僕は国語の教科書に載っている文章で「これは名文だ!」と思った文章がほぼないのです。
それよりも市販のビジネス書に本物の文章力を感じます。
(それでも、1、2割の良書のみですが)
つまり、名文でもなく、古臭い文章が現代文授業での教材だとしたら、確かに「こんなつまらない文章を読まされて何になるんだ!」と思う人が出てくるのも無理ないと思います。
まぁ本番の共通テストと違って、高得点が取りやすいのが普段の現代文の授業の試験ですから、要領よくやればよいのではないでしょうか?
共通テストの国語のような、訳の分からないテストに振り回されるのも、受験が終わるまでです。
それ以降は、法律系の資格や、公務員試験などで、まだ良くわからない悪文に遭遇するかもしれませんが、それを回避すれば、悩まされなくなります。
ご武運を祈ります!
ではこの辺で。(3492文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

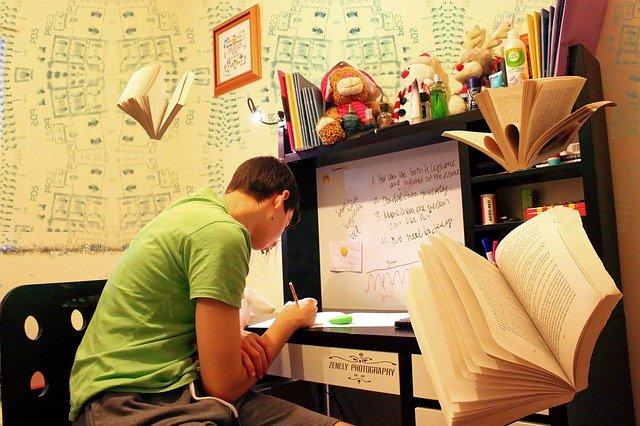







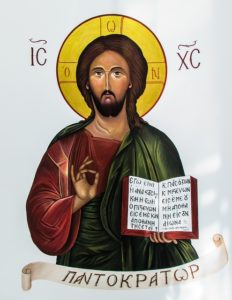
コメント