どうも、太陽です。(No170)
突然ですが、以下の記事によると、運命なんて信じない男性が65.4%もいたそうです。
運命を信じているのは約3割ということですね。
信じている人の理由として以下が挙げられています。
| ・ | 「生まれてからここまで、『なるべくしてなった』と思うので、運命だと思います」 |
| ・ | 「嘘みたいな出会いもあるし、全然努力してないやつが成功する場合もあるから」 |
| ・ | 「これまでの経験で、運命を感じたことがあるから」 |
信じていない男性の理由として、以下があります。
| ・ | 「自分の選択で人生が左右されると思う」 |
| ・ | 「自分の道は自分で切り開くものだと思うから」 |
| ・ | 「ないと断言する程の根拠もないが、数々のわかれ道くらいは選択権があるように思っていて、結果的に作り出すものと思っているから」 |
「運命に振り回されたくないという男性」は以下のように答えます。
| ・ | 「信じると翻弄されてしまうから」 |
| ・ | 「既に決まっていると思うとつまらないので」 |
| ・ | 「運命とかを考えていたら何もはじまらないと思うから」 |
詳しくは記事を読んでください。
では「運命についてどう向き合っていくべきか、どう考えるべきか」、「遺伝の観点から考えてみたい」と思います。
興味がある人は続きをお読みください。
1 遺伝率の説明。
いきなりですが、「生まれが9割の世界をどう生きるか」という本を参考にしてまとめます。
行動遺伝学という学問があり、双生児法という研究手法により、遺伝率などが明らかになっています。
詳しくは省略します。
(本を読んでください)
その人らしさが決まる要素として、遺伝、共有環境、非共有環境の3つがあります。
共有環境とは「家族のメンバーを似させようとする方向に働く環境」です。
家の習慣や子育てなどが該当します。
非共有環境は「家族のメンバーを異ならせようとする方向に働く環境」です。
遺伝と共有環境と非共有環境の影響率は行動遺伝学の研究により、発表されています。
ですが、あくまで統計的な処理によって求められる抽象的で概念的な値なのです。
具体的にどのような要因が「共有環境なのか、非共有環境なのか」については不明です。
家庭内のしつけは共有環境として働くことが圧倒的に多いのですが、子供自身の個体差によってしつけの影響も変わります。
地域や学校は非共有環境と思われがちですが、共有環境として働く場合もあり、一概に言えません。
非共有環境の本質は運であり、そのほとんどは予測もしない環境によって与えられるものです。
つまり、遺伝や意志に支配されない「運、偶然、ガチャ」にかなり多く左右されるのが人生なのです。
ところで、交友関係は家庭外なので、非共有環境と思われがちですが、遺伝も関与します。
ランダムに友達を決められてしまうのであれば非共有環境ですが、現実は本人の意志で友達をある程度は選んでいます。
人間はある程度自分と似たタイプ、つまり「知能が似ている人」を友達に選びがちであり、これは遺伝が関与します。
また、遺伝率は「親から受け継ぐ遺伝子の割合」ではありません。
知能の遺伝率が50%と言った場合、親の知能の50%が子どもに受け継がれるわけじゃないのです。
統計的に処理された値であり、僕もその詳しい仕組みをよく理解していません。
P24に書かれた文章をそのまま抜粋すると、以下になります。
統計学的に言えば、ある形質の表現型の分散(ばらつき具合)が、「遺伝子の分散によってどの程度説明されるか」を示したものが、遺伝率ということになります。
遺伝率についての詳しい説明は以下の本に載っています。
メンタリストDaiGoの師匠である鈴木祐氏の著書です。
かなりのお勧め本です。
さて、ジェニーさんのツイートを貼ります。
パーソナリティにおける遺伝率、共有環境、非共有環境の影響。
やる気、約6割が遺伝。
努力が出来ないことはどの程度が自己責任なのか。
総計1445万人の双生児を対象とした1958年から2012年までの2748件の研究を2015年にメタ分析したもの。 『無理ゲー社会』より。

2 平均への回帰。
「遺伝と環境でだいたい半分ずつで人生が決まる」っていうのはある意味、残酷です。
どうしようもない要因が半分を占めるわけですから。
まぁほとんどの形質は「40〜60%は遺伝の影響がある」と見なしておけば間違いありません。
さらに、スポーツ、芸術、数学などになると、さらに遺伝率が上がります。
(約8割以上)
しかし、平均への回帰という現象も起こります。
例えば、ものすごく出来のよい両親から生まれる子どもは、両親ほどには出来がよくない(それでも平均よりは出来がよい)確率が高くなるのです。
すごい親の子どもが、そんなにすごくならない事例は腐るほどあります。
逆に、ものすごく出来の悪い両親からは、それよりは出来のよい子どもが生まれる確率が高くなる幸運もあります。
KazukiFujisawaさんのツイートを貼ります。
平均的な両親から東大に受かるぐらいの偏差値の子供が生まれてくる確率は0.5%ぐらい。
親が東大卒だと学力が遺伝するから、たとえばこの確率が10倍ぐらいになる。
つまり5%ぐらい。
しかし、依然として20人のうち19人は親の偏差値に達しない。これが平均回帰や。
偏差値というか学力はかなり遺伝するし、環境も重要で、親が開成や桜蔭卒で、子に親以上の環境を与えても、子や娘が開成や桜蔭に受かるのは100人に1人か2人、みたいなんが、なんか僕は当たり前過ぎるぐらいに当然理解できるんだが、なんか人間はこういう論理が理解できないみたい、とても不思議。
「平均への回帰」をよく表しているツイートですね。
3 天才や外れ値が生まれるのは運?
まず、物理的に「同じように見える環境」を用意しても、その環境が各個人に対して「同じように働くとは限らない」、むしろ「同じに働かない」という前提を抑えておく必要があります。
遺伝と環境の関係をわかりやすく説明するために、セットポイントという言葉を著者は使っています。
ある人に音楽の才能があったとして、ある環境では確実に発現しますが、「違う環境ではまったく発現しない」といったものではなく、その関係は確率的なのです。
仮に、野球の能力について、1から5までの5段階で点数化できたとしましょう。
そして、ある人のセットポイントが3だったとします。
確率的には、その人の能力は3の場合が多いです。
ですが、特定の状況では4になる場合もありますし、逆に状況によっては2になる場合もあります。
状況が変わっても、「1や5の外れ値にはほとんどならない」、これがセットポイントのイメージです。
セットポイントは環境の側にもあります。
そこそこよい指導者がいる野球部であれば、セットポイントが4ぐらいあり、部員の能力を引き出しやすくなります。
逆に、あまり良くない指導者の野球部だと、セットポイントが2なので、部員が上達しません。
「部員個人が持つ遺伝的素質のセットポイント」と、「環境側のセットポイント」が足し合わさることで、その個人の発揮できる能力は変動するのです。
しかし、世の中にはへそ曲がりがいて、遺伝的素質のセットポイントが2なのに、たまたまた出会ったセットポイント2の指導者の何かにインスパイアされ、4の能力を発揮するかもしれません。
これを遺伝と環境の交互作用といいます。
(まぁ反面教師でしょうかね)
これは稀な出来事であり、複雑すぎて解明不能です。
しかも偶然でランダムな要素なので、非共有環境に組み入れられています。
以下の記事で僕は、イーロンマスクは「壮絶ないじめと本とプログラミングとの出会いが人生を変えた」と捉えました。
メンタリストDaIGoもかなりの外れ値の人物だと思っていますが、8年間もいじめに遭っていました。
幼少期の逆境は天才を生み出すのかもしれません。
(まぁほとんどは潰されて終わるでしょうけど)
また、非共有環境に関わる性質として、パーソナリティがあります。
知能は状況にあまり左右されず、安定して成果(点数など)が出ます。
一方、パーソナリティは状況によってけっこう変動します。
パーソナリティはBIG5(外交性、勤勉性、開放性、神経症的傾向、協調性)があります。
環境というのは膨大な要素で構成されており、一つ一つの要因の効果量は極めて微小で、なおかつしばしば遺伝的素質と複雑な交互作用をします。
誰にとっても同じに作用する単純な環境はありません。
ですから、天才が生まれるのは、遺伝と環境の複雑な相互作用であり、「教育で生み出せるものではない」ということでしょう。
4 教育の限界。
いきなりですが、ポリジェニックスコアという点数があります。
身長のような複数の遺伝子が関与する多遺伝子形質に対して用いられる、各個人の遺伝的に定義される形質を定量的に表した指標とあります。
さて、SES(社会経済状況)という用語があります。
学歴、収入、職業などを組み合わせて算出した社会経済状況のことです。
その学校に通う生徒のSESの平均の高低に関係なく、「ポリジェニックスコアの高い生徒」は数学のトレーニングに励みます。
SESの低い生徒が多く通う学校の場合は、ポリジェニックスコアが平均、もしくは低スコアの生徒は脱落しやすくなります。
逆に、SESの高い生徒が多く通う学校は、ポリジェニックスコアが非常に低い生徒だけが脱落します。
要は、ポリジェニックスコアの高い生徒はどんな学校でも優秀だけど、ポリジェニックスコアが平均あるいは低い生徒は「学校の良し悪しが関係する」という話です。
また、IQと学校成績についての調査があります。
学校成績に影響がありそうな要因として、以下の9領域を調査項目に入れました。
どの要因についても、遺伝と環境(共有環境+非共有環境)の影響がだいたい半分程度なのですが、学業成績の遺伝率は60%と、知能の遺伝率50%を上回りました。
学業成績の遺伝率60%のうち、30%は「知能の遺伝率」で説明できます。
それ以外の要因の影響度は以下の順になっています。
| 1 | 自己効力感。 |
| 2 | 学校環境 (家庭環境の影響はほとんどなし) |
| 3 | パーソナリティ (主に勤勉性) |
| 4 | 問題行動。 (親の評定と子ども自身の評定の両方) |
| 5 | 幸福感。 |
| 6 | 健康度。 |
このことから、勉強に関しては「やればできる」「自分な特別」などの「思い込みも大切だ」と言えそうです。
(自己効力感が1位ですからね)
ただし、自己効力感とはある意味、「成長マインドセット(やればできる)」という考えですが、以下の記事で「これを肯定するメタ分析と否定するメタ分析がある」と書かれています。
詳しくは記事を読んでください。
「やればできる」はすべての人に通用する万能薬ではないのですね。
次に、どんな人生を送るかは家庭よりも遺伝の影響が大きい事例の話として以下があります。
(教育の限界です)
教育達成度ポリジェニックスコアが高い人はSES(社会経済状況)の高い家庭で育つ傾向があります。
逆に、ポリジェニックスコアが低い人はSESの低い家庭で育つ傾向があります。
優秀な人は裕福な家庭に多いのでしょう。
東大に合格する親の世帯年収は6割以上が年収950万円以上ですからね。
しかし、SESが低い家庭で育った人でも、ポリジェニックスコアが高かった人は早期に言語能力を獲得して、上昇志向が強いという事実があります。
さらに、ポリジェニックスコアが高いほど、もともとのSESに左右されず、経済的に豊かになる傾向がありました。
つまり、親ガチャを乗り越える元々の素質の良い人(遺伝子がいい)がいたのです。
そして、学校の差は「そこまで学力や知能に影響を与えない」ことがわかっています。
集団のばらつきのうちのせいぜい20%かそれ以下の違いしか学校(非共有環境)は影響しません。
学力の差の50%は遺伝、30%は家庭環境(共有環境)です。
以上、教育の限界が垣間見れる話でした。
「生まれが9割の世界をどう生きるか」の本の一部を大雑把に僕なりのストーリーを基にして、まとめました。
この本は250ページもあり、相当に面白い本なので、ぜひもっと詳しく知りたい方は読んでみてください。
最後に、P6ページから運命についてかなり参考になる最高の文章を抜粋します。
世界は遺伝ガチャと環境ガチャでほとんどが説明できてしまう不平等なものですが、世界の誰もがガチャのもとで不平等であるという意味で平等であり、遺伝子が生み出した脳が、ガチャな環境に対して能動的に未来を描いていくことのできる臓器なのだとすれば、その働きがもたらす内的感覚に気づくことによって、その不平等を生かして、前向きに生きることができるのではないでしょうか。
僕のブログに辿り着いた人もある意味、偶然であり、運です。
僕のブログは「相当に参考になる記事が満載だ」と自負していますが、これに価値を感じて影響される人もいればそうならない人もいます。
僕のブログにたどり着くのは運ですが、それに影響されるかは遺伝や素養が関係しています。
人生が変わるきっかけとして、人や本や情報との出会いは大きいと感じます。
僕は運やコネに頼るのは嫌いな主義で、自分の能力やスキルのみを信じるのが合理的だと感じています。
しかし、大量に本を読むことが重要という点や独学は最強という視点に、高校生の時期から気づけたのもある意味、遺伝か運なのかもしれません。
大半の人は「学校や会社選び、コネ作り」に奮闘しますが、僕は「大量の読書と独学とネットでの出会いと情報収集ばかり」に力を入れてきました。
まぁもっと運やコネを信じて、権力者や有力者から気に入られたら、違う人生を歩んでいたかもしれませんが、仕方ありません。
僕は逆境下の中で、権力者の汚さを知りました。
そして、大半の普通の人が知らない知識を手に入れて、恵まれない人生続行中ですが、「面白い」と思っています。
最後に、再度、本を紹介して終わりとします。
同じ著者の前作も紹介しておきます。
メンタリストDaiGoの師匠である鈴木祐氏の著書も。
ではこの辺で。(5466文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。


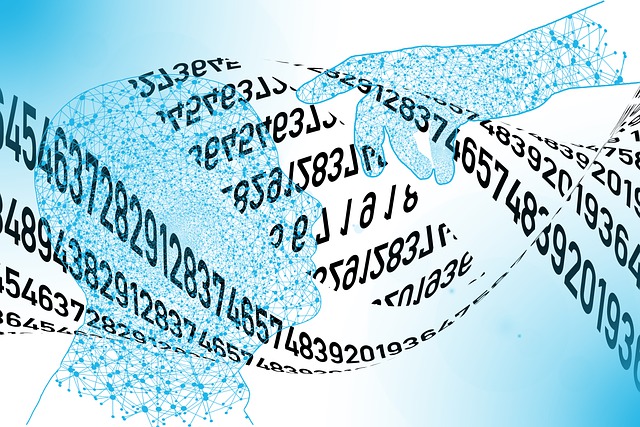




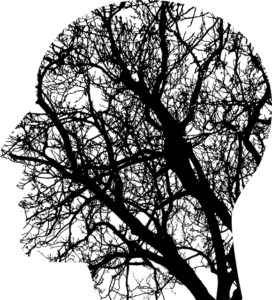
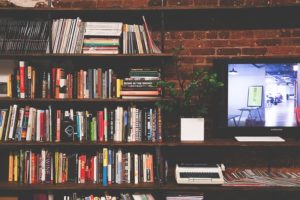


コメント