どうも、太陽です。(No78)
突然ですが、今回は大学入試での小論文に疑問を持ったので、「その点について述べていきたい」と思います。
大学入試の小論文といえば「国立大学での実施や慶應などの私立大学での入試」などあります。
これらの「会場で時間制限ありで受ける小論文入試」についての問題点を述べていきます。
会場での時間制限ありの小論文入試の一番の利点といえば、替え玉受験がしづらい点ですが、欠点もあるのです。
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 大学での論文と小論文試験はDaiGoやひろゆきの質疑応答と似ているという話。
大学で書く論文の場合、時間制限が緩く、会場での80分などの、時間制限がない上に、ネットや本などで調べたり、人に聞いてもOKでしょう。
いろいろな本を読んだり、人と議論したりして、自分の独自の見解を述べた論文を長い時間をかけて作り上げていきます。
落とすための試験ではないので、厳密な公正さなど必要なく、別に少々替え玉(他人が書いたとしても)されても、許容範囲な面はあります。
というより、他の誰かが仮に書いていたとしても、入念に確認できません。
それに対して、大学入試の小論文試験は点数化されるので、厳正で公正なジャッジが求められます。
ですので、「会場で時間制限あり・本人確認あり」の縛りがあり、替え玉受験しにくくしているのです。
そして、この際、求められる能力はメンタリストDaiGoやひろゆきの質疑応答(質問者のスパチャにすぐに反射的にどんどん回答していく。質疑応答は2時間〜3時間やる場合も)と似ているのです。
メンタリストDaiGoが「なぜ質問者の回答に数秒で答えを出せるか」といえば、過去にメンタリストDaiGoはたくさんの本を読んでおり、膨大な情報・引き出しがあったり、もしくは一度は考えたことがあるテーマだったりするからです。
あとは、質問者の質問に対して、メンタリストDaiGoが自分の過去の引き出しのなかのどの部分を持ってくるか、もしくは組み合わせるかを考えるだけなので、数秒で答えられるのです。
これを将棋に例えてみます。
プロ棋士であれば、定跡の範囲内であれば、1秒で反射的に指すことができます。
これは長年、研究してきたプロ棋士ならではの能力です。
対して、素人であれば定跡の範囲内であっても、見たことのない局面であり、1手指すのに考えるでしょう。
つまり、一度は考えたことがあるテーマや場面・局面であれば、人は答えをすぐに出せるのです。
また、将棋のような専門職の場合、狭い世界であり、子供の頃から一途にやり続けることがプロへの道です。
(ゴルフも同じようです)
対して、テニスのようなもっと複雑な局面や状況が訪れる競技の場合、「RANGE(範囲、幅)を広げる」、つまりいろいろなスポーツを経験してから、テニスに特化した方が柔軟にプレーでき、フェデラー選手のような一流選手になれるのです。
この話については以下の本に詳しいですので、興味がある人は読んでみて下さい。
さて、質疑応答において、スペシャリストが答えやすい質問もあるでしょう。
ですが、もっと範囲の広い、答えが見つかりにくい質問を投げかけられた場合、スペシャリストでは対処しきれず、「メンタリストDaiGoのようなゼネラリストに負けてしまう」と言えます。
話を戻します。
小論文の試験も、結局は「時間制限あり・ネットで調べるのがNG」であれば「自分の引き出しがいかに多いか」によって小論文の質が左右されます。
また、小論文試験の場合、引き出しが多い上に、それを「時間制限以内に組み合わせ、整合性・論理的でもあり、文章としてまとめあげる技能」が求められます。
加えて、PCならまだ修正がしやすいですが、シャープペンで書くのであれば修正がしづらく、厄介なことこの上ないです。
小論文試験の限界が見えた気がします。
テーマや課題について、何時間・何週間と考え続け、ネットや本で調べまくり、文章としてまとめあげる技能は問われていないのです。
こう考えると、僕の提唱した「日本論文プラットフォーム」にも支障が出てきます。
複数回の時間制限ありの小論文試験をいくら実施しようが、結局は過去の引き出しの多さ・組み合わせ力・文章力しか分からないからです。
もちろん、これはこれで必要な能力ですが、メンタリストDaiGo・ひろゆきのような質疑応答ができる人育成みたいな感じであり、熟考型人材は育てにくいのです。
メンタリストDaiGo・ひろゆきの質疑応答能力はニーズがあり、カリスマ性を感じられ、稀有な存在ですが、熟考能力・深く突き詰める能力までは小論文入試では問えないのです。
さて、次に、問うに値する質問をすることの重要性について述べていきます。
2 問うに値する質問をすることの重要性
アインシュタインは以下の名言を残したようです。
「私は地球を救うために1時間の時間を与えられたとしたら、59 分を 問題の定義に使い、1分を解決策の策定に使うだろう」
問題解決以上に、問題設定(問い)の重要性の強調ですね。
世の中には、「問うに値しない問いを考え、それを解こうとする人」がいます。
例えば、「人間はなぜ生きているのか?」という問いは、サルトルの「実存は本質に先立つ」じゃないですが、「生きているということは、なぜ生きているのか?やどう生きるべきかよりも先に存在していること」であり、「もう既に人間が生きている以上、そんな問いを考えても無駄だ」ということです。
野球で言えば、元メジャーリーガーのイチローが、「なぜ野球をするべきなのか?」を考えてばかりで、大リーグでの勝負に真剣に向き合っていなかったら、多くの人に感動を与えられなかったはずです。
つまり、考える意味もなく、問う意味もない質問を投げかけて、労力を消費している人は「大した人間になれない」ということです。
ビジネスでいえば、企画立案や方向性でかなりビジネスの成否が決まり、方向性が悪い努力をすると、正しい努力じゃなくなり、多くの努力は徒労に終わります。
だからこそ、アインシュタインは59分も「問題の定義(問い・方向性)に時間を使うべき」と強調したのでしょう。
(もちろん、ビジネスの世界は最近はVUCA時代なので、「ある程度筋のいい企画案を考えたら、すぐに実行し、試行錯誤して実行する段階を増やした方がいい」とも言えます)
「私とは何か?」の自意識についての問いなら、自意識の本を読めばいいですし、単なる本当に「自分(私)とは何か?」という問いなら、自分探しであり、そんなことを考えるより、「行動し、試行錯誤して掴みとっていくものだ」と思います。
問いでも、問うに値する問いを量産する人は、アイデアマン・企画立案者・研究者であり、「問題解決案まで提示しなくても価値はある」と思います。
または仮説を提示するだけでも、問題解決へのたたき台となり、価値はあります。
あと、悩み相談にせよ、問う人にせよ、「何かしらのその人の仮説を提示した方がいい」と感じます。
「ここまでは自分なりに仮説を考えてみたが正解かどうか分からない」「自分の仮説を越える問題解決案を提示して欲しい」という人だと、時間短縮ができ、問題解決へのスピードが上がるからです。
これをしない人は、相手の時間を奪っています。
ともかく、問うに値する問いを考え、ブレーンストーミングやディベートをするべきでしょう。
問うに値しない問いで、ブレーンストーミングやディベートをしても無駄骨じゃないでしょうか?
加えて、「日本人はなぜ、他人に助けを積極的に求められないのか?」という問いを立てた人がいましたが、これは多くの日本人が悩む点なので、問うに値する問いです。
僕の解答は、企業でいえば「システムで解決する」というものです。
本当に体調が悪く、深刻な場合「レッドカード」を出し、ちょっと余裕がなくきつい場合「イエローカード」を出すなどですね。
日本人は自己主張が苦手なので、こういう風に「仕組みで主張しやすくする工夫は大事だ」と思います。
ただし、悪用・濫用される懸念は残ります。
(イエローカードの多用・連発ですね)
事故などで、公の場所で助けを求める際には、こういう仕組みは役立たず、自己主張する訓練をするしかないかもしれません。
アメリカ人などは日本語が下手でも、「日本語を上手に喋れる!」と堂々と主張するのに対し、日本人は謙遜して「英語を上手に喋れません」とよく言います。
また、アメリカでは裁判が多く、訴訟大国ですし、他民族国家なので、自分の主張をしないと相手にわかってもらえない、伝わらない文化を経験しているので、自己主張をする国民となりました。
日本では阿吽の呼吸が通じ、自己主張をすると和を乱す存在とみなされ、村八分の可能性もありますし、子供の頃から自己主張をする訓練がされていないので、自己主張をする国民にはなりませんでした。
日本ほど、権力者が「国民を飼いならし、扱いやすい国はない」と思います。
コロナでこんなに遅い対応をしていたら、アメリカなどだったら暴動でしょう。
日本人はおとなしいですし、デモや暴動をあまりしません。
もっと政治家やメディアなどに怒るべきであり、「文句を言うべきだ」と感じます。
参考になる箇所があったら幸いです。
最後に、繰り返しますが、知識の幅を広げる重要性を説いた以下の本が本当にオススメです。
ではこの辺で。(3922文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

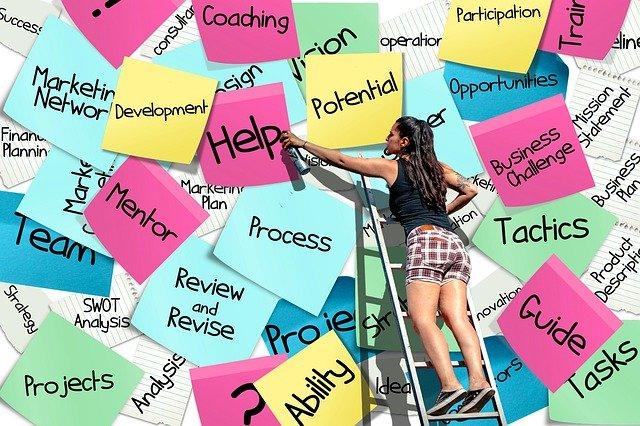







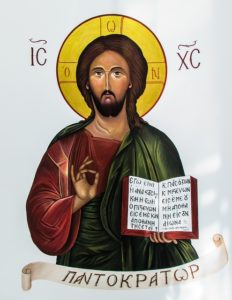
コメント