どうも、太陽です。(No136)
突然ですが、日記を用いたアメリカの調査では、人は平均して1日に約1回、学生の場合は約2回ウソをついていました。
最近のインターネット調査研究では、24時間の間にウソをまったくつかなかった人は6割程度だといいます。
逆に言えば、1日の間だけでも、4割の人がウソをついていることになります。
世の中には息を吐くようにウソをつく人がいて、病的ウソと呼ばれます。
また、ウソをつくことにためらいを感じず、一見表面上は魅力的なサイコパスが100人に1〜2人の割合でいます。
今回は、以下の項目を「あなたはこうしてウソをつく」という本から引用・まとめをしつつ、考察していこうと思います。
| 1 | そもそもウソとは何か? |
| 2 | 人はどうしてウソをつくのか? |
| 3 | ウソは見抜けるのか? |
| 4 | どういう場合に、そしてどういう人がウソをつくのか? |
| 5 | ウソをつくとき、脳では何が起きているのか? |
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 そもそもウソとは何か?
いきなりですが、ウソはありふれています。
経歴詐称、脱税、浮気・不倫、データ改ざんや捏造などが明らかになることは多いです。
ウソの定義は「真実でないこと。また、そのことば。いつわり」とあります。
つまり、ウソの話し手や聞き手の心理状態は考慮されていなく、情報の正確さのことを言っています。
学術的な定義だと、ウソが情報の不正確さ(真実じゃない)を大前提とした上で、相手を欺こうとする意図があるかどうかが重要です。
つまり、ウソは「意図的に相手をだますような、真実でない言語的陳述」という定義です。
また、ウソは基本的に、言語的なコミュニケーションが多いです。
で、煙信号やモールス信号や手話といった手段を通して伝えることもウソに含むとしています。
加えて、「だます」「あざむく」とは、「本当でないことを本当であると思い込ませること」であり、「欺瞞」という言葉でも表せます。
「欺瞞」は言葉を使うとは限らず、表情やジェスチャーも含みます。
欺瞞という広い概念の下にウソがあるのです。
さて、人がウソをつく理由は次の3つの次元で分類されます。
| 1 | 自分のためか、他人のためか。 |
| 2 | 利益を得るためか、不利益や罰を避けるためか。 |
| 3 | 物質的な理由か、心理的な理由か。 |
1は「利己的なウソか、利他的なウソか」ということです。
就職の面接で、企業に受かるためにエピソードを作るのは利己的なウソです。
また、自分の後輩を出世させるために、「彼は頑張っているよ」と社長などにアピールするのは利他的なウソです。
2の「利益を得るためか、不利益や罰を避けるためか」という話ですと、前述のウソの例はどちらも利益を得るためのウソになります。
「不利益を避けるためのウソの事例」として、病気の母親に対し、自分の会社の経営が上手くいっていなく、心配をかけたくないために「会社の調子がいいよ」と言うモノがあります。
こっそりおやつを食べてしまった子どもが、叱られたくないためにごまそうとするウソは、罰の回避のためです。
3の「物質的な理由か、心理的な理由か?」の話は、分かりやすいです。
会社のお金を横領するために帳簿を改ざんするのは、金銭(物質的)という理由によるウソです。
他人から賢くみられたいために知ったかぶりをするウソは心理的な理由になります。
また、「ウソをついてでも出世をして、財産から名誉まであらゆるものを手に入れたい」となると、物質的・心理的の両方を含むでしょう。
この3つの話はお互いに独立していないので、複数の理由が混在するケースもあります。
ウソをつく理由は多様で複合的なのです。
ウソはその理由や状況によっては、人間関係を円滑にするための潤滑剤としても機能します。
2 ウソは見抜けるか?
ウソを見抜けると有益な場面として、犯罪、企業での採用面接、結婚相談所など多くあります。
言語的な内容をもとにウソかどうか判断するやり方は、「自分が確かに事実を把握している・自分の記憶に間違いがない」という前提がなければ、うまく機能しません。
で、実際問題、いつも「相手の発言内容のウラを取れる」とは限りません。
相手の発言内容の真偽が不明な場合は、私たちは相手の発言内容以外、つまり非言語的な手がかり(言いよどみや言い間違い、声の高さや話す速さ、視線やまばたき、手や足、頭の動きや姿勢など)から判断しようとする人もいるでしょう。
ウソと真実を識別できる研究によると、もっとも高い正答率のもので73%です。
もっとも正答率が低いものは31%であり、研究全体の平均正答率は約54%なので、コインを投げて裏表を予測できる確率よりも少しましな程度にすぎないのです。
ちなみに、特定の職業、例えば「CIAの職員やウソに関心のある臨床心理学者」などは、7割程度の正答率でウソを見抜けます。
私たちはウソを見抜くことを妨げてしまう「真実バイアス」(他人の言っていることを真実であると判断する傾向が高いこと)があります。
で、これがあるからこそ、仕事や遊びがある程度、スムーズに進むのです。
(イチイチ、半分くらいの言動について疑っていてはキリがありません)
逆に、真実バイアスとは逆のバイアスがあり、相手の発言を必要以上にウソだと考えてしまうバイアスもあり、警察官など普段からウソに対峙している人達が持っています。
ウソに敏感であっても、真実をウソと判断すると冤罪につながる可能性もありますし、「ウソを正しく見抜けている」とは言えません。
ウソをウソとして見抜ける正確性だけでなく、真実を真実として見抜く正確性も同じくらい大事です。
以下の記事には「ウソを上手に見抜く方法」が書かれています。
また、私たちはウソを見抜く能力を過大評価する傾向もあります。
加えて、私たちは真実を知りたい一方、内容や状況によっては真実を知りたくない欲求もあるので、そういう現実逃避効果から、ウソに気づきにくくなります。
これらの要因は、いずれも「ウソを見抜く側の要因」ですが、こうした複数の要因がある上に、ウソはしばしば、真実のなかに目立たないように紛れ込んでいる場合もあるのです。
最近の研究によると、ウソをつくのが上手だと思っている人ほど、「シンプルなウソをつき、真実の中にウソを埋め込み、もっともらしい説明を追加する戦略を取る」といいます。
また、正直に答えることでかえってウソつきと疑われるような場面(例えば、テストでクラスの全員がほぼ50点しか取れなかったのに、たまたま自分だけ100点を取れた場合)、むしろ少しウソをつくことで、ウソつきと思われることを防ごうとする研究結果もありました。
こうした要因が複合的に関与すると、「ウソを見抜くのはほぼ不可能だ」と思われます。
しかし、「1度切りのウソならバレない場合もある」でしょうが、一度ウソをつくと辻褄を合わせないといけなくなり、何度もウソをつくといずれバレることも十分ありえます。
生理反応に基づいた虚偽検出はポリグラフ検査と呼ばれますが、詳しい解説は本をお読み下さい。
(脳派による虚偽検出、fMRIによる虚偽検出も載っています)
また、「人間の記憶自体が不完全なもの」という前提も置いて置かないとマズイでしょう。
加えて、ウソを見抜けたとしても、「ウソをつこうとした意図や決断の領域まで考えないといけなくなる」とも言えます。
3 どういう場合にウソをつくのか?
人がウソをつく場面として、試験前になると「学生の親族が亡くなった」と報告して、時間稼ぎをする場合があります。
さて、「人がどれくらいウソをつくのか」を規定する要因は、状況要因と個人要因の2つに大別されます。
状況要因とは「どのような状況で人はウソをつきやすくなるか、という個人の外部の要因」を指します。
個人要因とは「どのような個人の属性がウソのつきやすさと関連するか、という個人の内部の要因」を指します。
試験前の事例でいえば、試験前という状況が「不正の頻度を大きく引き上げている」と思われるので、「状況要因の典型例」と言えます。
ウソをどれくらいつくか、すなわちある個人の「正直さ」については、「個人要因よりも「状況要因が決定的に重要だ」と言われていました。
例えば、子どもなら、親や教師には頻繁にウソをつくのに対し、友人相手にはそれほどウソをつかない、つまり「個人の中でも状況によって大きく行動が異なること」が判明しています。
つまり、「あの子はウソつきで、いつもウソばかりついている」というわけではなく、子どもたちのウソというのは状況特異的なのです。
子どもたちの正直さは、性格や品性といった一貫した内部の状態があるわけじゃないのです。
もちろん、個人要因がまったく無関係というわけでもなく、正直さと関連する個人要因もあります。
ただし、相対的には状況要因がより大きなウェイトを占めています。
アリエリーの実験デザイン「数字合わせ課題」が事例として示されていますが、省略します。
(詳しくは本で)
「多くの実験参加者が少しだけウソをつく」という結果は、ポジティブな自己イメージを損なわない範囲でウソをつく、という「自己概念維持理論」から説明できます。
つまり、「自分は正直者」とどうにか納得できる範囲でちょっとだけウソをつく、のです。
また、ウソをついたことを告白する場面では、「人は部分的なウソの告白にとどめる割合が多かった」という結果が出ています。
ウソによって得られる利益を得つつも、「どうにか自分のことを正直者である」と正当化したい傾向があるのです。
加えて、「疲れている」とウソをつきやすくなります。
「自我消耗」という概念があり、「人間の意志の力や自制心が有限である」とする考え方です。
有限であるがために、「自制心をずっと働かせつづけるのは難しい」ので、ウソをついたという解釈です。
ですが、再現実験によると、「自我消耗は再現できない」となり、研究結果が疑問視されています。
人間には決断疲れ、つまり、長時間の意思決定を繰り返すことにより、物事の判断や決断の質が低下してしまう現象があります。
決断疲れがあるとなれば、午後と午前なら、「午後にウソをつきやすくなる」と思われます。
しかし、朝型の人にはこうした現象が生じるものの、「夜型の人はむしろ午前のほうがより多くのウソをつく」という結果も報告されています。
これまでの事例は、「疲れによって自制心を働かせにくくなり、結果としてウソをつきやすくなる」というメカニズムでした。
ただし、自制心に影響を与えるのは、疲れだけじゃなく、例えば決断を下すまでの時間制限の有無も大きく影響します。
以下の2つの研究報告があります。
| 1 | シャルヴィらによる、時間を十分に使えない状態ではウソをついてしまうという結果は「私たち人間が本性としてはウソをつく」と言える。 |
| 2 | カプラロらによる結果は、その逆で、「本性としては正直に行動する」と言える。 |
ウソをつくかどうかの判断には、ウソをつくことで得られる利益の種類も関わってきます。
これまでの研究では、他人の利益になるようなウソなら、道徳的にはあまり悪いこととされず、「罪の意識を感じにくい」とされています。
ところで、オキシトシンを鼻から吸引すると、他者を信頼しやすくなるそうです。
さらに言うと、オキシトシンを吸引すると、自己利益よりも、所属集団の利益を重要視するようになります。
しかし、オキシトシンとウソの研究を疑問視する声も上がっています。
ウソつきは同じウソつきを好み、「正直者が相手の不正(ウソつき)にタダ乗りする」という実験も載っていますが、詳しくは本で。
ウソがウソをよぶ、いわゆる「どうにでもなれ効果」があります。
ウソを何度もつくと、本当のウソつき常習犯になるのです。
不正に手を染めると、深みにはまっていくので、最初の1歩を防がないといけないのです。
自我消耗やオキシトシン、モーセの十戒、モラル・ライセンシング効果については、再現されなかった問題が発生しているので、要注意です。
4 どういう人がウソをつくのか?
どういう人がウソをつくのか、すなわち、ウソの個人要因に着目します。
「正直さに与える要因」としては、個人要因よりも「状況要因」のほうが強い影響をもっていますが、個人要因を無視していいわけではありません。
「男女差のウソの研究」によると、男性は女性よりも利己的なウソをつくことが多く、「利他的なウソは女性で多く見られる」とのことです。
こうした男女差は、ウソをつく相手の性別による影響も受けます。
「男性の利己的なウソは相手が男性の場合に多く、一方で女性の利他的なウソは相手が女性のときに多い」そうです。
その後の個別の研究だと曖昧になりがちですが、ウソが自身に利益をもたらす状況では、男性のほうがよりウソをつく傾向があるようです。
年をとると、ウソのつき方が変わってきます。
小さいときは否認などに単純なウソが多かったのが、大きくなってくると、より高度なウソが増えます。
ウソの頻度は発達とともに上昇し、青年期にピークとなり、その後下がっていき、ウソの上手さも同様の「逆U字形を描く」とされています。
若者がウソをつくのは、「リスクをとるからだ」という解釈もあります。
経済学と経営学を専攻している学生はウソをつきやすいそうです。
(あくまで全体の傾向です)
自分が銀行員であるというアイデンティティを意識した場合のみ、「ウソをつきやすくなった」という研究報告もあります。
欲張りな人ほど、ウソをつくという研究報告もあります。
創造性が高い人ほど、ウソをつくという研究報告もあります。
有力な説明として、創造性が高い人ほど、「自分が正直者であるというポジティブな自己イメージを維持するための理由づけが上手なのではないか」というものがあります。
つまり、創造性を駆使することで、さまざまな理由づけでもって、自分がウソをついたことを正当化できるのです。
ただし、創造性の高さは主観報告のみなので、自分の創造性についての自己評価の高さがウソをつきやすくなることに影響しているのかもしれません。
「知能が高ければウソをつきやすくなるわけじゃない」という研究報告もあります。
(知能とウソのつきやすさの「有意な関係性はない」とありますが、「完全に関連ない」とは言い切れません)
知能が高ければ上手にウソをつけますが、ウソに伴うリスクも正しく評価できるので、一見すると知能とウソとの間に明確な関連がなかったとしても、ウソをつこうとする意思決定に至るまでの個々のプロセスでは、「知能によって違いがある」可能性が残ります。
ウソのつきやすさにはさまざまな個人要因が関わっており、あまりウソをつかない人もいれば、たくさんウソをつく人もいます。
しかし、「病的ウソ」と呼ばれる、「目的もなく常識では考えられないほどウソをつく人」もいます。
「病的ウソ」と似た用語として、「空想虚言」という表現があり、空想と現実の区別がつかなくなり、「ウソをついている本人もウソなのか真実なのかわからなくなっている」という状態です。
なお、病気でないのに病気だと偽る「詐病」がありますが、病的ウソとは異なります。
詐病は基本的には、その動機が明確なものです。
(利己的な動機)
「ミュンヒハウゼン症候群」という言葉もありますが、詳しくは本で。
病的ウソは解明されていません。
自閉症とウソとの関連については研究はまだ少数です。
以下の記事にあるように、自閉症の人は重大な違法行為や間違いを見逃さず、「傍観者にならない」と言う研究報告もあります。
「個人の正直さは世界各国で異なっている」という研究報告もあります。
「ウソをつくとき、脳で何がおきているのか?」については諸略します。
(詳しくは本で)
5 サイコパスと嘘との関係と僕の意見。
サイコパス傾向が高い人ほど、ウソをつくかどうかの意思決定の反応時間が早く、「葛藤の検出に関わる前部帯状回の活動が低い」のです。
サイコパス傾向が高い囚人は、ためらいなくウソをついているわけで、彼らの不正直さはより自然に発現しています。
一方、サイコパス傾向が低い囚人は、ウソをついてはいるものの、その意思決定に何らかの葛藤を感じ、躊躇しながらウソをついているのです。
これは「意図的な不正直さ」と考えられます。
人間にとって正直に行動するという善行は、自然に行える場合もそうでない場合があります。
さらにはウソをつくという悪行も、「自然に行う場合とそうでない場合がある」ということです。
そしてこれらは、少なくとも報酬への感受性やサイコパス傾向といった要因が、「調整的な役割を果たしている」と思われるのです。
私たちが自然に正直な行動をするか、ウソをつくのかは、道徳的「初期設定」によって規定されるものであり、「前頭前野の活動はその個人の道徳的初期設定を覆すように作用すること」を示した論文があります。
前頭前野の活動は単に「正直に行動するか、ウソをつくか、どちらかに作用する」というわけではなく、その個人の道徳的初期設定(正直者にとっての正直な行動・ウソつきにとっての不正直な行動)に反する行動を形成するものと解釈できます。
以上、ここまで。
僕はネット上で、人の年齢を当てることをよくしますが、その際、心がけていることあります。
男女ともに若い人の場合、ピンポイントで当てにいきます。
20代前半までですかね。
で、男女ともに40代だと思われる人の場合、30代または30歳と予想することで、相手に「若い!」と思ってもらえたと印象づけることで、「今後の関係構築を良好にしよう」と狙っています。
30代前半の場合、「27歳ぐらい」と予想することで、これも「若い人と思ってもらえた!」と印象づけることもあります。
まぁ、33歳ぐらいなら、ピンポイントで当てにいってもいい気がしますけどね。
35歳以上だと思った場合、真面目に当てにいってはいけない、またはそもそも年齢を聞かないほうがいい気がします。
(一応、男の場合なら、年齢の確認のため、30歳ということで「若いと思っていた!」と思わせ、悪い印象を残さなくします)
若い男女の場合は年齢を聞いてもまったく失礼じゃないんですよね。
「あなたはこうしてウソをつく」という本は興味深い事例が満載で面白い本なので、ぜひ読んでみてください。
ではこの辺で。(7409文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。

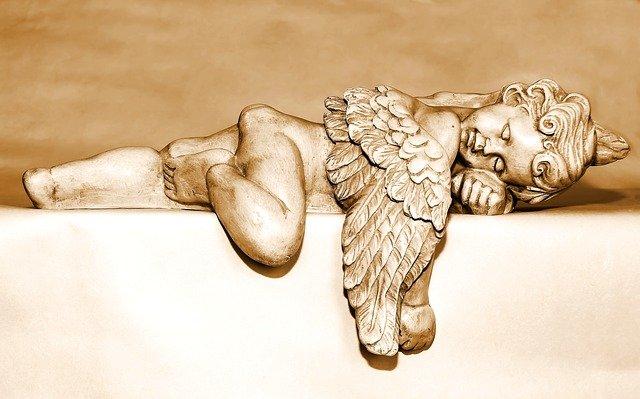








コメント