どうも、太陽です。(No30)
突然ですが、皆さんは、「超一流、一流の違い」を理解していますか?
今回は、両者の違いを「具体化して、示したい」と思います。
一流とは僕は「問題を解決する人」だと思っています。
超一流は「それを超える人」です。
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 超一流とは?
突然ですが、「(特に高度なレベルや厄介な)問題解決のできる人が一流人だ!」と、ほとんどの人は、僕が指摘しなかったら、感じるのではないでしょうか?
ですが、超一流はそれとは別次元の人なのです。
それは「そもそも問題を起こさない人」です。
問題が起きる前に「未然に防げる・予防・防止できる人」が、超一流の人なのです。
問題が起きてしまったか、問題を起こすのを止められず、起きた問題を意気揚々と解決する人は、超一流ではなく、一流の人です。
問題を解決するのではなく、そもそも問題が起きなければ一番いいのですから。
政治家や経営者であれば、「攻めの政策や利益を上げる人が一流だ」と感じるでしょうが、「問題がほぼ起こらない、一見すると、目立たない人」こそが超一流です。
「問題が起こらない」ということは、統治や経営などがきちんと機能しており、危機意識も万全ということが言えますからね。
問題は起きてしまってからでは、手遅れなことも多いです。
ある人に聞いた事例を書きます。
会社の重要なデータを扱っている彼と同棲中の女性がいて、女性は彼の重要データ入りのズボンを洗濯してしまい、データが消えてしまったのです。
その結果、彼は大事な取引先を失い、それが尾を引いて別れ話になったのです。
挽回できるとなれば、彼が新たな取引先を再度開拓すればいいのですが、世の中なかなか上手くいきません。
こういう事例もあるのです。
または、自動車事故などで相手を死なせたら、取り返しがつきません。
(ちょっとくらい酒を飲んでもいい、スマホをいじってもいい(ポケモンGOなどをプレイする)という油断が命取りになるのです)
ただし、問題を起こさない人には、超一流の人の他に、もう1種類のタイプがいて、「困難なことに挑戦しない人」が該当します。
困難なことに挑戦しないのですから、厳しい試練や問題が起こりにくくなります。
こういう人は超一流ではありません。
よく面接で、「人生で一番苦労したことは何ですか?」と聞かれますが、ここでできない人ほど本音では「苦労したことなどない」と思っているケースがあります。
そして、「苦労したことは何があったか」と答えをひねり出そうとします。
もちろん、天才肌の人なら東大合格でさえ「苦労は本当にしていない」かもしれませんけどね。
このように「超一流とは問題をそもそも起こさない人」なのです。
(そもそも困難なことに挑戦していないで、問題が起きていない人は除きます)
2 超一流の定義と超一流になるには?
超一流を、「難しい問題にチャレンジしていながら、そもそも問題を起こさない人」と定義するとします。
そうであると仮定するなら、結果を出し続ける、つまり勝ち続ける人ほど、「高度なことにチャレンジしていながら、問題を起こしていない(課題として浮き彫りになっていない)と言える率が高い」と言えます。
もちろん、資源制約下にある人が大半であり、戦力差もありますから、単純に勝ち続ける人だけが超一流なわけではありません。
ですが、高い勝率を誇る人ほど問題・課題を予防している率が高い傾向にあり、「超一流と言える」と僕は感じます。
ところで、サッカーについては以下の意見を僕は持っています。
サッカーは勝負事であり、if(たられば)がありまくる世界です。
本当にできる人(超一流)ほど、実は課題が出てこないで勝ってしまう人なのです。
一流ぐらいになると、試合を終えてから課題が出てきます。
「起きた後に初めて課題だ」と気付くのです。
(そういう人が大半です)
しかし、超一流になると結果が出てしまうので、課題だとすら認識されません。
なぜなら、課題だと認識する前に事前に気づいて、対処しておくからです。
だからこそ、課題だと初めて認識することはありませんし、たとえ問題が起きても想定内になるのです。
(分かっていたけど、実力不足でやっぱり露呈した弱点ということになります)
では、超一流になるにはどうすればいいのでしょうか?
3 超一流になるための方法。
それは、予測力をつけることです。
または、常に仮説や予測をし、試行錯誤を続けることです。
具体例を出しましょう。
人との会話において、普通の凡人は相手が話をし終わってから、相手の話を理解できることが多いです。
ですが、超一流になると、相手の話を予測しながら聞いているのです。
何となくの話の流れから「こういう展開になるのだろうな」と考えながら聞き、自分の中で当たっているか確認する習慣があります。
(この際、相手に「こういうことでしょ?」と気づいていることを言うと、相手の気分を害す恐れがあります)
サッカーの西野監督も日々、細かいことで予測する癖をつけていたそうです。
僕も超一流を目指して、普段の会話から始まり、細かいところで日々、仮説と予測をする習慣をつけています。
これをやると、結末が訪れる前に課題を発見できるようになるのです。
課題が見えたら予防策を取れますので、予防策を取らないよりは、結果が出やすくなりますし、後で課題だったとなることが少なくなります。
(つまり、想定内になります)
起業の世界では「とりあえず動けや動いてから考えよ」と言われますが、それは1勝9敗でもいいからであり、勝負ごとの世界(スポーツなど)では、1回でも負けると敗退することがあります。
失敗が許されない世界では、なるべく失敗の確率を下げなければならず(そうじゃないと敗退)、そのためには、予測力と仮説力をつけて、事前に課題を察知することが必要なのです。
例えば、アスクルで倉庫火災事件がありましたが、これを対岸の火事と見ずに、Amazonなどの物流倉庫を持つ企業は重要視すべきです。
Amazonは特に物流倉庫が重要要素なので、これが火災になったら被害は甚大です。
だからこそ、徹底的な火災などの事故予防をしなくてはいけません。
4 まとめ。
超一流はこのように日々、問題にチャレンジしつつ、課題となる前に、仮説と予測力で事前に課題だと認識して対処しておいて、結果を出しやすくするようにしています。
未然に察知して課題を認識し、対応策を取っておき、たとえ実力不足やリソース不足などの理由により結果がでなくても、少なくとも想定内にはできるということです。
一流は後で、「これが課題だったか」と初めて認識し、想定外のことが多くなり、防止ができないのです。
これが一流と超一流を分ける、些細な差だと想います。
最後に、この記事の内容をまるで書籍化したかのような本が出ているので紹介しておきます。
「上流思考──「問題が起こる前」に解決する新しい問題解決の思考法」
ではこの辺で。(2977文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。






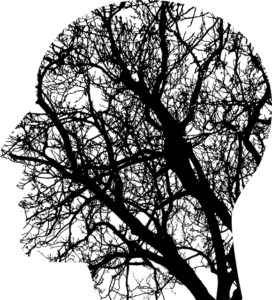
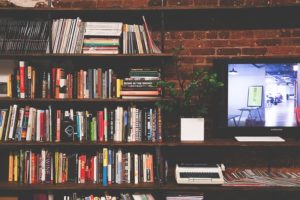


コメント