どうも、太陽です。(No174)
突然ですが、以下の記事で、「Gravityのある部屋においての議論のやり方」について書きました。

音声通話アプリGravityで行われていた議論のやり方の件や、集合知について考えてみる
その部屋では「科学的に有意であると思われる真実?みたいな答え」を素人集団が出そうとしていることに僕は気づきました。
で、それは限界があると思い、さらに新たなテーマが浮かんだので記事化します。
興味がある人は続きをお読みください。
1 多方面戦略(多様性)と選択と集中戦略について。
いきなりですが、国単位の話をまずします。
国家において、多方面戦略、つまり多様性を確保できるのは「資金的に豊かな国である」という前提があります。
逆に、貧しい国は選択と集中戦略を採らざるを得ません。
そして、自然科学においてはほぼ一定の法則があります。
人文科学においては、心理学では「科学的に有意と思われる多数派の傾向」という真実が一応ありますが、結局は「人それぞれ」と言えてしまう部分があります。
社会科学においては、特に、法律はそこまで解釈の余地が少なく、人それぞれの部分が少なくなります。
「人それぞれ」というのはある意味、多様性確保であり、豊かな国の証拠です。
ですが、人それぞれの意見を尊重し、存在を認めてもいいですが、「支持すべきかや、関わるべきかは義務ではない」と思います。
例えば、多様な人とどう関わるかは、人それぞれ問題であり、自由度があります。
で、多様な人の存在はなるべく認めるべきですが、支持したり、関わるかどうかはその人次第です。
つまり、リソースが限られているので、「多様な人への守備範囲の広さを確保できるかどうか」は別問題なのです。
ところで、守備範囲を広げるとは「アンテナを多方面に立てること」でもあります。
食わず嫌いせずに少しでも興味を持ったら、記事などを読むのはアンテナを立てている人の特徴です。
ただし、「有限なリソース(時間や労力など)を消耗する」という欠点もあります。
しかし、守備範囲が広いと、異分野融合が起きて、画期的なアイデア発見につながる確率が高まります。
話を戻します。
選択と集中は「貧しい国の基本戦略」であり、効率的ですが、弊害もあります。
それは「画期的なアイデアが生まれない」ということです。
(守備範囲が狭いのです)
また、何がブレイクするのかわからない世の中なので、最初から決め打ちの選択と集中はリスクにもなりえます。
多方面戦略(多様性の確保)はリスク分散の利点もありますが、コスト(資金など)がかかる欠点もあります。
よく言われることですが、多方面戦略でアンテナを幅広く立てておいたほうが、その数多くの研究の中から画期的なアイデアや発明が生まれる可能性があります。
(ただし、コストがかかり、無駄撃ちが多くなります)
対して、選択と集中戦略は少ない分野に資源を集中しており、ローコストであり、当たれば効率がいいですが、外れたら、大損失です。
一番、理想的なのは「かなりの目利きがいる」という前提で、選択と集中をできることですが、かなり難しいです。
(ヒットするモノを事前に察知して、投資できないです)
2 Gravity議論部屋での作法
ここで、マクロの問題とミクロの問題に移ります。
統計的に有意な多数派に当てはまる傾向という真実は、マクロでの結論です。
対して、究極的な真実(人それぞれ)は、ミクロの話です。
(サンプル数少ない)
で、研究対象で重視すべきなのは、最大多数の最大幸福に仮に則れば、マクロでの結論である科学的研究です。
もしくは、外れ値の画期的なアイデアや発明を生み出す天才や、難病なども研究対象にすべきかもしれません。
外れ値を研究対象にするのは「コスパが基本的には悪い」ですが、天才研究であれば例外であり、リターンが大きそうです。
まずは「多数派に当てはまる、多数の人が助かる、幸せになる研究」を重視すべきでしょう。
優先順位としては、ざっくり分けて、多数派(統計的に有意)>天才>少数派>難病など になるでしょうか。
本来なら、AIや量子コンピュータがかなり発展して、個人個人に最適な処方箋を出せるようになれば、理想的です。
ですが、コスパが悪く、まだ実現不可能なので、統計的に有意な多数派に当てはまる真実の科学があります。
ここからが本題です。
Gravity議論部屋では、統計的に有意な多数派に当てはまる傾向の科学的真実を、素人集団が打ち出すのはほぼ無理なのです。
であるなら、「以下の目的が有益である」と思われます。
それは人文科学の人それぞれの分野のテーマにおいては、「統計的に有意な真実など存在しない」と見なし、多方面にアイデアを出し合い、各自が役立つと思ったモノを持ち帰るという考えです。
人間は本来、自分ごとに関心があり、「自分に役立つモノ」を最優先します。
で、ほとんどの人は科学者気質ではなく、多数派の意見などそこまで重視せず、自分に当てはまり、役立つ意見だけ聞きたいのです。
そうだとすれば、正解はないのですから、多方面に雑多なアイデアを出し合い、良し悪しを決めつけず、「各自が良いと思ったモノ」を持ち帰ればいいのです。
僕や科学者気質の人はそれを理解できず、正解を求め、相手を批判的に捉えていました。
ですが、そもそも人文科学の分野での素人集団の議論の場では「正解などない」のです。
(あくまで学者の世界ではなく、素人集団のGravity議論部屋の話)
しかし、ここで一つだけ問題があるとすれば時間的制約です。
僕の理想像をいうと、議論の場においては賢い人が4人ぐらいで少人数で議論するのが効率的です。
Gravityでは6人まで議論の場に上がれますが、そこにあまり賢くない人が混じると、無駄な方向に論点などが流れてしまうのです。
もちろん、正解はなく、「各自にとってどれが役立つか」は不明なのですが、考察の深いところに到達するのが遅くなったり、もしくは「到達できないこと」になります。
賢い人同士の議論は情報処理能力が速く、論点がそこまでずれず、しかも考察が深い境地にいきます。
まぁ正解はないのですし、何をもってして賢いか判定するのも微妙な問題ですが、賢くない人同士の議論だと、無駄が多く、考察も深まらず、タイムオーバーになる可能性が大です。
これが僕が考えたGravityでの議論の作法です。
3 会社ではどうすべきか?
ついでに、「会社での議論はどうすべきか?」についても書いておきます。
Gravity議論部屋においては「正解がなく、多方面に話を展開し、各自が良いと思うところだけを持ち帰ればいい」という結論でした。
で、会社においては時間的制約は当然考えるべきですから、賢い人をなるべく集めて、効率よく、多方面に議論を展開し、考察も深くしたほうがいいです。
国単位の研究の話だと、予算の限界で、多方面戦略(多様性確保)は採りづらいのですが、議論の場では多様な人材間での多様なアイデアは良いです。
つまり、選択肢が多くなり、その数多くのアイデアの中から、「意思決定者がどれを採用するか?」を決められます。
もちろん、全ての人にいい顔はできませんし、誰かにとっては害を被るアイデアが採用されるかもしれませんが、仕方ありません。
しかし、選択肢が多い中から決めるのと、そこまで多くない筋の良いアイデアから採用するのとで、「成果にどれだけ反映するか?」は不明です。
1000つのアイデアを出して、筋の良いアイデアを10本に絞り、そこから採用するのと、100つのアイデアを出して、同じく筋の良いアイデア10本に絞り込まれる可能性もあります。
つまり、後者の方では、的確率が高い人(賢い人)同士が議論してアイデアを出した可能性もあります。
的確率7割の人と、的確率3割の人では、やはり効率が違います。
的確率とは、結果的に生み出したアイデアや意見が後から見て正しかった確率のことです。
ともかく、「何かを決める」ということは「他の何かを選ばない」ということですし、誰かにとっては得や有利になり、誰かにとっては損害や不利になったりします。
意思決定者のセンスが問われます。
政策立案者やアイデア発想者と、それらを採用する意思決定者は別かもしれません。
責任重大なのは意思決定者の方です。
また、以下の記事ではスティーブ・ジョブズが「優秀な社員を信用して、叡智を集めていたこと」が書かれています。
スティーブ・ジョブズの教え|最高のリーダーは周囲の人間を信頼すべし
最後に、会議には「目的別に3種類ある」という記事を紹介します。
https://news.yahoo.co.jp/articles/07217b98250d4912854de02affb3fb17565e1b82
「会議の7割を1人でしゃべり続ける上司」にストップをかける必殺技「承認サンドイッチ」とは?
| ・ | 共有のための会議 (会議全体の65%) |
| ・ | 決定のための会議 (会議全体の13%) |
| ・ | アイデア出しのための会議 (会議全体の22%) |
目的をはっきりさせた上で、会議に臨むと、会議時間は11%短くなるそうです。
最後に、僕の議論においての強みを自覚したので、書きます。
自分の得意分野というか、強みとして、たたき台としての仮説(ボケ)を作り、誰かが正確な知識をもとに反応して解説してくれたり、科学の実験をしてくれたり、さらにその解説に僕が「変な角度からツッコミ(クリティカルシンキング)できることだ」とわかりました。
「沈黙は金」は不用意に敵をつくらない処世術ですが、そんなことより、問いを解くのが純粋に楽しいわけです。
そして、問いの解決のためには「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」で「男子家を出ずれば七人の敵あり」の格言どおり、7人の敵を作ろうが、実験思考で試すほうが優先されます。
僕のたたき台(仮説)を面白がってくれる人が、貴重な人です。
それを叩き潰そうとか、「失礼な奴だ」や「マナーがなっていない」という人は、面白がれる精神がないか、余裕がない人だから、関わらないほうがいいと気づきました。
あとは僕はクリティカルシンキングでツッコミを問いの解決のために入れまくるので、そのツッコミを「不快だ!」とか、「マナーがなっていない」など、嫌う人間とも関わらないほうがいいですね。
異論や反論を「そういう意見もあるのかぁ」と僕はある程度、楽しめます。
しかし、それを楽しめない人間がいて、「マウンティングだ!」と捉えます。
もしくは、異論や反論があって、それが正しいとなったら、楽しめるどころか「負けたけど、認めるしかない」みたいなマインドの人もいます。
YESマンに囲まれるのを「良し」と捉える人がいて、絶望的に相性が悪いです。
YESマンは何でも肯定してくれるので、楽です。
逆に、クリティカルシンキングでツッコミを入れて来る人(正しい意見だとしても)がいたら、改善しないといけない?から面倒くさくなります。
IQについての記事も貼っておきます。
https://president.jp/articles/-/79549
IQ118の弁護士はIQ85の建設作業員より競馬予想が下手だった…「本当の頭のよさ」を突き止めた珍研究複雑な要素を組み合わせる能力はIQで測れない
才能についての記事は以下です。
https://toyokeizai.net/articles/-/737888
超天才と凡人「遺伝によって差を分ける」は本当か多数の才能の持ち主を研究して見えてきた真実
今回の記事がなにかの参考になれば幸いです。
ではこの辺で。(3533文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。







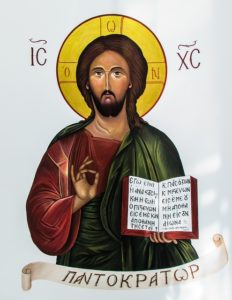

コメント