どうも、太陽です。(No97)
いきなり、「人間なんて生き物は所詮、大したものではない」という言葉を言われ、戸惑う人もいれば、「人間なんてそんなものだよね。。。」と冷めた人もいるかもしれません。
僕が「なぜこんなタイトルをつけたのか?」興味がある人は、続きをぜひお読みください。
根拠がよく分かるはずです。
さらに、そういう「大したものじゃない生き物にならないためのアドバイス」も書いてあります。
1 人間が大した生き物じゃない理由
「人間なんて生き物は、所詮、大したものではない」という主張をしたいと思います。
順々に論じていきます。
1 自己中心性。
まず、人間は基本的に「自己中心型、利己的」です。
極端に言えば、「自分さえ良ければいい」という自分中心が本質です。
社会で生きていくうちに、他者のことも考えられるようになりますが、本質は「利己的」です。
(社会に出ても、「自分さえ良ければいい」という人はけっこういます)
そういう自己中心的な人は、ポジショントークをよくします。
自分の経歴、生育歴、能力などを正当化したいのです。
とにかく、「自分が上なんだ、自分が主人公なんだ」という人も、それなりにいます。
しかし他者を立てる、他者を応援する人もいます。
そういう人は、自分の人生をどこかで諦めた人か、引退した人でしょう。
または、マネジメントをする立場になったので、他者を育てるのです。
さて、自分が中心ということは、例えば性格診断で「自分は凄いタイプの性格」だと診断結果が出たら、自分のことは誇らしげに語りますが、他者が「自分もけっこう凄いタイプの性格」の結果が出たと言っても、それはあまり目にかけません。
他者が凄いタイプの性格だとは、「そう簡単に認めたくないから」です。
自分中心の人は「自分だけには良い結果が来る。他者には来ない」と思っています。
35歳を越えた客観的には魅力が劣る女性が「私には白馬の王子様が来る」と信じているようなものです。
こういう自分中心の思考は、世の中を歪めて解釈しているので、客観的に冷静に自分を見つめなおした方がいいです。
客観的に見ても、「自分は凄い能力がある」と思えるのなら、それは本物でしょう。
ここで、「自分だけは絶対に大丈夫」と人間は思い込んでしまう心理を紹介します。
258名の大学生に「将来、あなたが大人になったとき飲酒上の問題を抱える可能性はどれくらいありますか?」という質問をしたところ、「自分に起きる可能性」から「他人に起きる可能性」を引き算してみたら、マイナス58.3%という結果になりました。
「他人はアルコール中毒になるかもしれないけど、自分だけは絶対に大丈夫」ということです。
さらに、「自分が将来、自殺未遂する可能性」と「他人が自殺未遂する可能性」を尋ねて引き算してみると、マイナス55.9%という結果でした。
加えて、「結婚後数年で離婚してしまう可能性についてはマイナス48.7%、「40歳以下で心臓発作に見舞われる可能性」はマイナス38.4%、「性病にかかる可能性」はマイナス37.4%でした。
「自分は他人とは別」という思い込みがすごいことがわかります。
もしくは、自分のことは「状況によってなされた行動」だと解釈し、他者のことは「内面によってなされたこと」と解釈します。
自分の評価と他者への評価が異なるのです。
「自分の行動の過ちは状況が悪かった、環境、時代が悪かった」と言い、「他者にはあなたの性格や行動を反省せよ」と言うのです。
2 人間が大した生き物じゃない理由の続き
話しを戻します。
人間はほとんどの人が自己中心的であり、自分中心なので、相場観も養われていないし、客観的に自分の評価を下していません。
ここまで読んでいた方は、げんなりしている人もいれば、「人間ってそんなもんだよね」と同意している人もいるでしょう。
2 自分は平均より上という思い込み。
根拠は「自分が平均より上だという人がほとんどを占める」ことから言えます。
アメリカの学生の93%、スウェーデンの学生の69%は「自分は平均以上の運転技術を持っている」と答えました。
ほとんどの人が「自分は平均より上」という解釈だと、平均値に収まりません。
つまり、大多数が勘違いしているのです。
客観的に判断するというと、「現実を見ろ!」と説教されているみたいで、「嫌だな」と思うでしょうが、その現実を直視することから始めないと、進歩がありません。
自己イメージを高めることは「成功、勝者への道」ですが、ここには危険性があります。
それは自己イメージがスキル構築を伴わずに高まると、過信、慢心につながる点です。
つまり、客観的な実力より、自分の自己イメージの方が勝るのです。
もちろん、自己イメージは低いとやる気になりませんから、自己イメージを高めることは重要です。
ですが、過信、慢心せず、きちんとスキルを着実に身につけ続けてこその、自己イメージの高さが前提です。
実際、鬱病の人は「自分は平均より上」だとは思わないで、客観的な自己評価をしています。
つまり、健全な人は「自分は平均より上」だと思えるからこそ、自己イメージを保てており、これが鬱病並みに「客観的な評価を自分に下す」と、病気になるのです。
このことからも、人間とは自分の評価さえも客観的に正確には下せないのです。
しかも、大多数に当てはまる傾向です。
こう考えると、「人間なんて生き物は所詮大したものではない」と僕は思ってしまいます。
自分の評価さえ正確に下せず、さらに、他人には自分より下の評価を下す性質ですから。
僕も少なからず、「そういう傾向は人よりは少ない」とはいえ、ありますから自分も含めて「人間なんて大した生き物じゃない」と思います。
(客観的に自己評価を下そうと、努力はしています)
3 自分は善人で世の中は悪人だらけ。
さらに、「自分は善人で、世の中は悪人だらけ」という思い込みも人間の大多数は持っています。
この現象が起きる理由は、自分に都合のいいことしか記憶していないからです。
他人にしてあげた親切な行動は覚えていても、他人がしてくれた親切な行動はすぐに忘れます。
3 大した人間じゃないと言われないためのアドバイス
ここまで読んで、かなりげんなりした人もいるかもしれませんが、もう少し頑張って読んでください。
ここからは励ましも入りますので。
僕の文章を読んでいる方には、自分の実力を客観的に評価して、そこを出発点に地道に努力して欲しいのです。
そして他者は「大した評価能力を持っていない」ということを頭に入れて欲しいのです。
他者は「自分の能力は人より上だ」と思いがちであり、さらにポジショントークをし、あなたを下に見てきます。
ここで、「客観的に見て、実力がきちんとある人のアドバイスは聞いておいた方がいい」とアドバイスします。
そういう人は「自己評価も他者評価も的確だ」と思うからです。
しかし、大抵の人は「評価能力がない人」ですから、そういう人の意見をまともに聞いても仕方ないのです。
例えば評価能力がない人から、いくら悪口を言われようが、その人の評価自体が誤っている可能性が高いのですから、まともに聞いたらあなたにブレが出てきてしまいます。
つまり、「きちんとした実力者以外のアドバイスは、聞かない方がいい」のです。
もちろん、表面上は聞いたフリはしておくのも処世術であります。
(反抗し過ぎると、人間関係がおかしくなるので。とはいえ、「自由闊達に意見を言える職場の方がいい」と思います)
または、自分が全ての面で、他者より上回っている完璧な人はいませんから、他者が自分より勝っている専門分野については、聞いてもいいでしょう。
他者の専門分野をそれぞれから学べば、あなたは最強になります。
本当は総合的にはあなたの方が上になりますが(きちんと、他者の専門分野を吸収したら)、自分より上回っている専門分野の人から吸収すれば、他者のいいとこどりができるわけですから、実力が格段に上がるのです。
これが自分より格下だからと「自分より専門分野では上回っている人」の意見を聞かなければ、損です。
つまり、人には強み・弱みがあり、弱みの分野については意見をスルーし、強みについてはきちんと聞けば、いいとこどりができるのです。
そのためには、ある程度の自分の判断軸を作らなければなりません。
「何が正しいのか」は初心者のうちは分からないからです。
「相手の専門分野が正確なのか」、または「自分より上なのか」、きちんと判断するには、ある程度の勉強や知識が必要です。
もし、膨大な情報に支えられた判断軸がないと、やみくもに権威に頼る人間になります。
「誰が言っているのか」だけに意識がいき、内容で判断しなくなるのです。
そうはならないためにも、僕の上達法を取り入れ、自分の判断軸を作り、他者の「評価能力がない人」に、極端に振り回されないで「生きて欲しい」と願います。
4 大した生き物じゃないを覆そうとしている人たち
ここで、人間への希望について語ります。
いままで人間に幻滅していた人も、多少は希望が持てるかもしれません。
タイトルで、「人間なんて生き物は所詮、大したものではない」と書きましたが、この自己評価と他者評価の欠陥を真剣に正そうとしている人たちがいることも、付け加えておきます。
それは航空業界が典型例でしょう。
彼らは失敗から学びます。
詳しくは「失敗の科学」という本に書かれています。
良書です。
ほとんどの人は失敗をしたら、隠すか無視するのに対し、航空業界は人の命、安全がかかっているので、失敗から学び改善するフィードバックシステムが整えられているのです。
そういう人や業異こそ、称賛されるべきだと思います。
医療業界は昨今まで(アメリカの事例ですが)、隠蔽体制が顕著でした。
警察もそうです。
しかし、失敗した場合、隠さないでオープンにし、共有しないと改善しません。
人間の愚かさ(自己評価や他者評価の欠如や失敗から、学ばない)を改善するのは、大事なのです。
さて、人間は、ベイズ統計学の理論のように日々、自分の能力が平均より上か下かなどの確率を、アップデートする生き物です。
しかし、大半のアップデートの情報は自信過剰に傾きます。
しかし、「自信過剰なのが良いとき」もあります。
根拠のない自信がある人は「自身がそう本当に思い込んでいる」ので、そういう人に時々騙される人が出るほどです。
恋愛にせよ、戦いにせよ、自信がある人の脅しなどに、屈してしまうのです。
また、楽観主義の方が行動を促しますし、行動は生存に有利に働きますので、やはり自信過剰はこの場合、良い方向に働きます。
上記にも書きましたが、鬱病の人は自己評価は健全ですが、病気になったら困ります。
自信過剰にも良い点はありますが、反省や失敗から学んで、自己評価と他者評価をきちんと判断できるようにしたいものです。
「人間なんて所詮、大したものではない」というタイトルが覆るような生き方を目指す人が、増えればと思います。
最後に、あまりにも失敗を繰り返すと、ある時点で「人は失敗から学ばなくなる」という記事を紹介します。
外科医をサンプルとして研究していますが、同じ外科医でも高度な医学的訓練を受けていたり、専門的な患者ケアの知識や経験がある外科医は、そうでない外科医に比べて、失敗の蓄積でパフォーマンスが下がり始める閾値が高かったとあります。
つまり、「高い学習能力を持つ外科医は、失敗から学ぼうとする意欲も高いため、失敗の繰り返しにより生じる負の感情や諦めへの耐性が強かったのだろう」と結論づけています。
逆に言えば、低い学習能力の外科医は、失敗をあまりにも繰り返すと、失敗から学ばなくなる、「もうダメだ、自分には無理だ」と意気消沈し、学習や挑戦を諦めるということです。
こういうことを僕は肌身で感じていたので、なるべく失敗しないように、失敗率を極限まで下げ、やる気の持続性を保っています。
ではこの辺で。(4810文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献






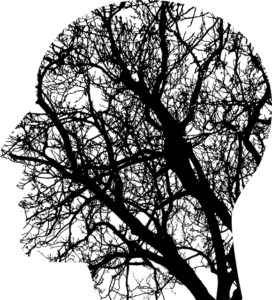
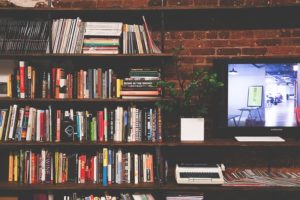


コメント